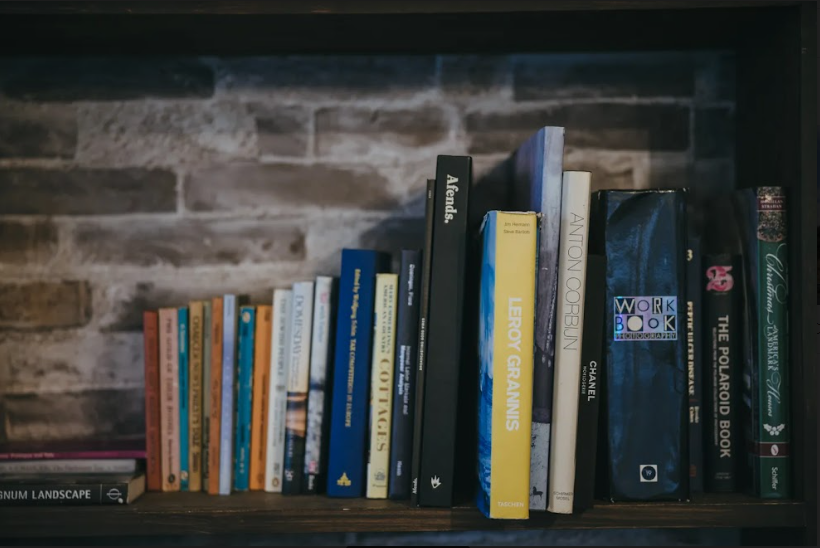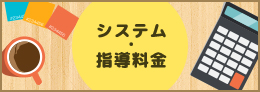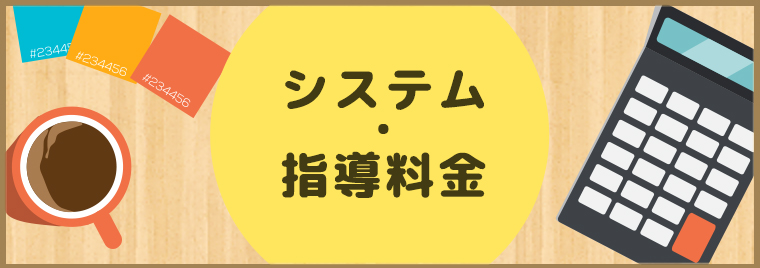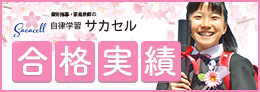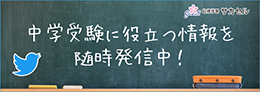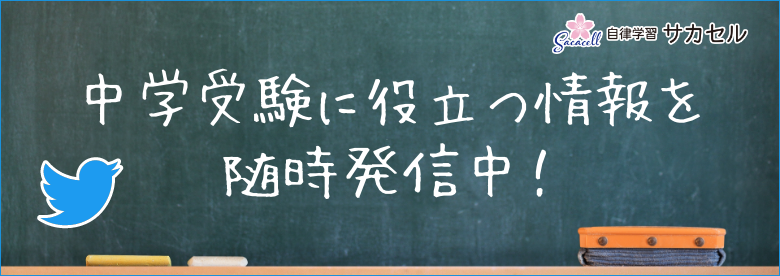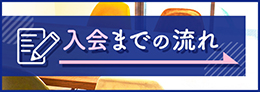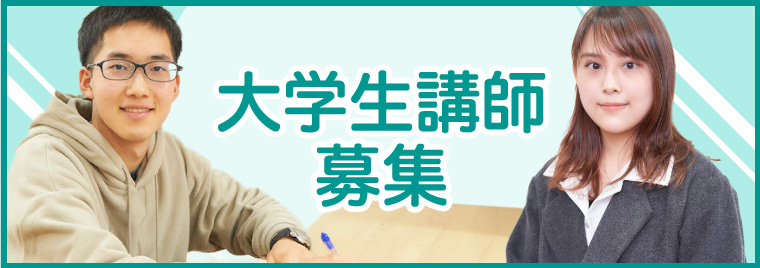卒業式のシーズンですね。
「元」受験生たちが巣立っていく姿を目にして「受験生として」「最高学年として」決意を新たにしている「新」受験生の皆さんも多いのではないでしょうか。
さて2024年3月23日(土)にSAPIX新6年生3月度復習テストが実施されます。
新6年生になって、初めての範囲のあるテストです。
復習テストなのでテスト結果によるコース昇降はありませんが、毎回のテキストの徹底理解がSAPIXにおける学習の根幹です。
新6年生以降の学習の定着度を測る絶好の機会なので、入念に準備をした上で挑みましょう。
ここからはSAPIX新6年生3月度復習テストの算数に関して、お話を進めていきます。
【概要】
制限時間:50分
配点:150点満点
試験範囲:平常01~平常05と基礎力トレーニング2月号
出題数は25~30問で、平均点は80点弱になることが多いです。
SAPIXにおける範囲のあるテストとしては標準的な難度で、2023年の平均点も78.7点でした。
ただ2021年には64.4点と低めの水準になったこともあったように、決して難度が安定しているわけではありません。
目標点を明確に定めるよりも、試験中に取るべき問題を的確に見極め、確実に得点するよう心掛けましょう。
【重要度】
2024年3月3日に昇降無制限の組分けテストがあったばかりなので、今回の復習テストにおけるコース昇降はありません。
「コース昇降に関わらないなら…」と気が抜けてしまうSAPIX生も少なくはありませんが、その意識は絶対に払拭しましょう。
冒頭でも言及したように、SAPIXにおける学習の基本は「毎回のテキストを徹底的に復習し、定着させる」ことです。
今回の試験範囲は「数の性質」「平面図形」「割合」「速さ」という中学受験最頻出分野ばかりです。
来たるべき受験本番から逆算すると、非常に重要な単元が続く3月度復習テストの重要度は非常に高いと言えるでしょう。
【各テキストのポイント】
平常01 数の性質
「約数・倍数」と「素因数分解」をテーマとする、難度はやや高めのテキストです。
「約数・倍数」に関しては復習内容が中心なので比較的取り組みやすいでしょう。
B3 C3 D3のようなベン図を用いての整理の仕方には、今の時点で慣れておく必要があります。
D1の公約数の考え方も自分の言葉で説明できるレベルまで、理解を深めておきましょう。
E1も有名問題です。
どうして差の公約数が割る数□になるのか正しく理解しておきましょう。
「素因数分解」を利用する整数問題は、難関校でも頻出のテーマです。
今回はアプローチ⑤の「何回割れる?」のマスターが最重要事項になるでしょう。
ただ式の形を覚えるのではなく「素因数分解して何が何個出てくるか?」に注目して、問題ごとに丁寧に検証できるようになることを目指しましょう。
今回のテキストなら、どのSAPIX生もD1までは理解しておく必要があります。
偏差値55を目指すならE2まで頑張りたいところでしょう。
それ以上を目指すとしても、E3は(4)の難度が極端に高くなっています。
算数の平均偏差値が65を越えるなど、よほど算数に自信がない限りE3は(3)まで出来れば充分です。
平常02 平面図形1
「図形の移動」と「30°の利用」をテーマとするテキストです。
「図形の移動」は
1:「動きの境目」に注目して丁寧に作図し、
2:長さや角度などの数値を記入し、
3:式を立てて、×3.14の計算の工夫も心掛けて、最後まで解ききる
という丁寧な作業が必須です。
このうち「円の転がり移動」は復習単元が中心なので取り組みやすいでしょう。
B3 C3の「センターラインの利用」は使える場面と使えない場面をきちんと理解した上で活用しましょう。
なんでもかんでも「中心が動いた距離×幅」と考えてしまうと非常に危険です。
区別がつかないならば丁寧に作図し計算しましょう。
A1 B1 C1 D1などの「全体-白」は新出の内容です。
「図形式」で「何から何を除くのか」を視覚的に整理できると良いでしょう。
B2 C2 D2などの「30°の利用」も中学受験では「常識」として理解しておくべき内容です。
「30°60°90°の三角形⇒正三角形の半分」という視点を身につけておきましょう。
その他の問題ではD3が大切です。
「点と直線の最短距離⇒垂直」という考え方を吸収しておきましょう。
今回のテキストなら、どの生徒もD2までは理解しておきましょう。
偏差値55を目指すなら全ての問題を解けるよう、努力を重ねましょう。
最後のE3は計算自体は面倒ではあるものの、考え方は決して難しくはありません。
平常03 割合
「食塩水」「損益」「歩幅と歩数」の3つがテーマになっているテキストです。
「食塩水」は復習内容が中心で易しいでしょう。
面積図を用いた混合と、食塩/全体を用いたやりとりに慣れることが出来れば、このテキストは卒業です。
E3は数値が汚いだけで発想は難しくありません。
計算が合わないならばアプローチ⑦で解法を確認しておきましょう。
「損益」は問題の種類が多岐にわたり、難度は高めです。
まずは言葉の意味を正しく捉え、問題に応じて式や図で適切に整理できるよう練習しましょう。
D1 E2を正しく理解して解きこなせるようになれば、このテキストの損益の問題は卒業です。
「歩幅と歩数」は、このテキストの最重要新出単元です。
まずは導③で用語の意味を正しく掴むことから始めましょう。
「歩幅(の比)×歩数(の比)=速さ(の比)」の関係を、言葉のメモも意識して、表の形で見やすく整理しましょう。
解く際にはB4⇒D3⇒C1⇒E1の順に取り組めると、スムーズに理解を深めることが出来そうです。
今回のテキストなら、まずはCまで全てとD3を正しく理解しておきましょう。
偏差値55を目指すなら掲載されている問題は全て解けるようにしておきたいところです。
平常04 割合2
「倍数算」をテーマとするテキストです。
6年生の全カリキュラムの中でも有数に易しく学習負担は小さめなので、このテキストの学習の際に平常01~平常03の復習にも時間を割きたいところです。
このテキストでは掲載されているほとんどの問題を「問題文に沿って立式」⇒「消去算として処理」という流れで処理することが可能です。
SAPIXの解答例の線分図で処理しても良いですが、慣れれば式のほうが早く正解までたどり着くことが出来るでしょう。
解答の際は「いつ」の「何」を問われているのか常に確認するよう心掛けましょう。
D3とE3は「表で整理する」がテーマの「倍数算」とは種類の異なる問題です。
長大な問題文のどこに注目すべきかを適切に判断しましょう。
今回のテキストならD3 E2 E3 E4以外は全て解けるようにしておきましょう。
偏差値55を目指すなら、掲載されている問題は全て解けるよう練習が必要です。
平常05 速さ1
「旅人算と比」をテーマとする重要テキストです。
「線分図での整理の仕方」「比の使い方」「速さと時間の逆比」「平均の速さ」などの重要解法を使い分けられるようにしていきましょう。
「線分図での整理」は「同じ時刻に同じ記号」「距離や時刻や速さを書き込む」等を意識しましょう。
B1やC1で線分図における距離の比の活用の仕方を掴めると良いですね。
D4やE3、E4などの処理量の多い問題も、丁寧に処理していけば問われている内容自体はシンプルです。
「平均の速さ」=「合計の距離」÷「合計の時間」も、このテキストを通して身につけておくべき知識事項です。
最も重要な内容はD3です。
線分図で状況を整理しても良いですが、この問題を通して「距離が同じ時、速さと時間は逆比」という受験算数における最重要事項を常識として昇華させましょう。
このように「旅人算と比」に関する様々な問題が掲載されているテキストなので、マスターすべき問題も多いです。
D3までは全てのSAPIX生が正しく理解しておきたいところです。
偏差値55を目指すなら、D4 E2 E3 E4も取り組んでおきましょう。
E1は「線分図での整理」の有名問題ですが、初見では適切な方法で整理できない生徒も数多く見られます。
1度解いて理解しておけば充分でしょう。
【3月度復習テストにおける算数の対策】
新6年生になって初めての範囲のあるテストです。
該当テキストは5冊と決して多くはないですが、中学受験における頻出分野を数多く扱うので、良い準備をして試験に挑みたいところです。
テストに向けた準備としては、何はともあれテキスト内容の復習が最優先です。
アプローチや実戦編で今まで解いてきた問題を再確認し、重要事項の定着を図りましょう。
類題演習としてはB5の冊子形式のデイリーサピックスの使い勝手も良いでしょう。
多くのSAPIX生はデイリーサピックスまで手が回っていないので、初見の数値設定の問題として復習テスト対策に充てられるのではないでしょうか。
「同じテーマでも問われ方が変わると対応できない…」という悩みを持つSAPIX生は、他塾の問題集を併用した学習も効果的です。
四谷大塚の「予習シリーズ」は解説も詳しく教科書のように使えますが、SAPIXの問題の類題演習という観点では、グノーブルの「G脳ワークアウト算数」が最も互換性が高いでしょう。
SAPIXとほぼ同等のカリキュラムではありますが問題のバリエーションが更に多いので「解きつくした!もう解いていない問題がない!」という猛者でも満足できる構成になっています。
手に入るならば過去問演習も効果的です。
「問われ方が変わった場合の類題演習」 「50分の時間配分の確認」等を意識して、新しい年度から数年分に取り組むことが出来れば、得点力の向上に直結します。
ただあくまでもテキスト内容の知識が身に着いてから取り組みましょう。
理解が浅い状態で過去問に取り組んでもどれが典型題でどれが応用問題なのか適切に判断できず、充分な学習効果は得られません。
【総論】
SAPIXにおける受験算数は、6年生の夏期講習いっぱいまではテキスト内容を吸収し、解法知識を増やしていくことが最優先です。
その点で今回の3月度復習テストはコース昇降こそないものの、6年生序盤の学習の定着度の確認として非常に重要度は高いです。
好成績を残すことが出来れば、今の勉強法を継続させられれば夏期講習前までの算数の学習で困ることはあまり想定されません。
もし適切な準備をしたはずなのに上手くいかなかった場合は、早急に学習法を見直す必要があります。
原因が究明できない場合は是非ともご相談ください。
このように今回のSAPIX6年生3月度復習テストの結果は、ある意味これから半年の6年生の学習の成否を占うとも言えそうです。
良い準備を重ねて、SAPIX6年前期という大波を乗りこなしていきましょう!
SAPIXに関して、より詳しく知りたい方はこちらをご覧ください!
塾選びから合格(または転塾)までSAPIX完全解説
にほんブログ村にも参加しています。ぜひ下のバナーをワンクリックで応援もお願いします!