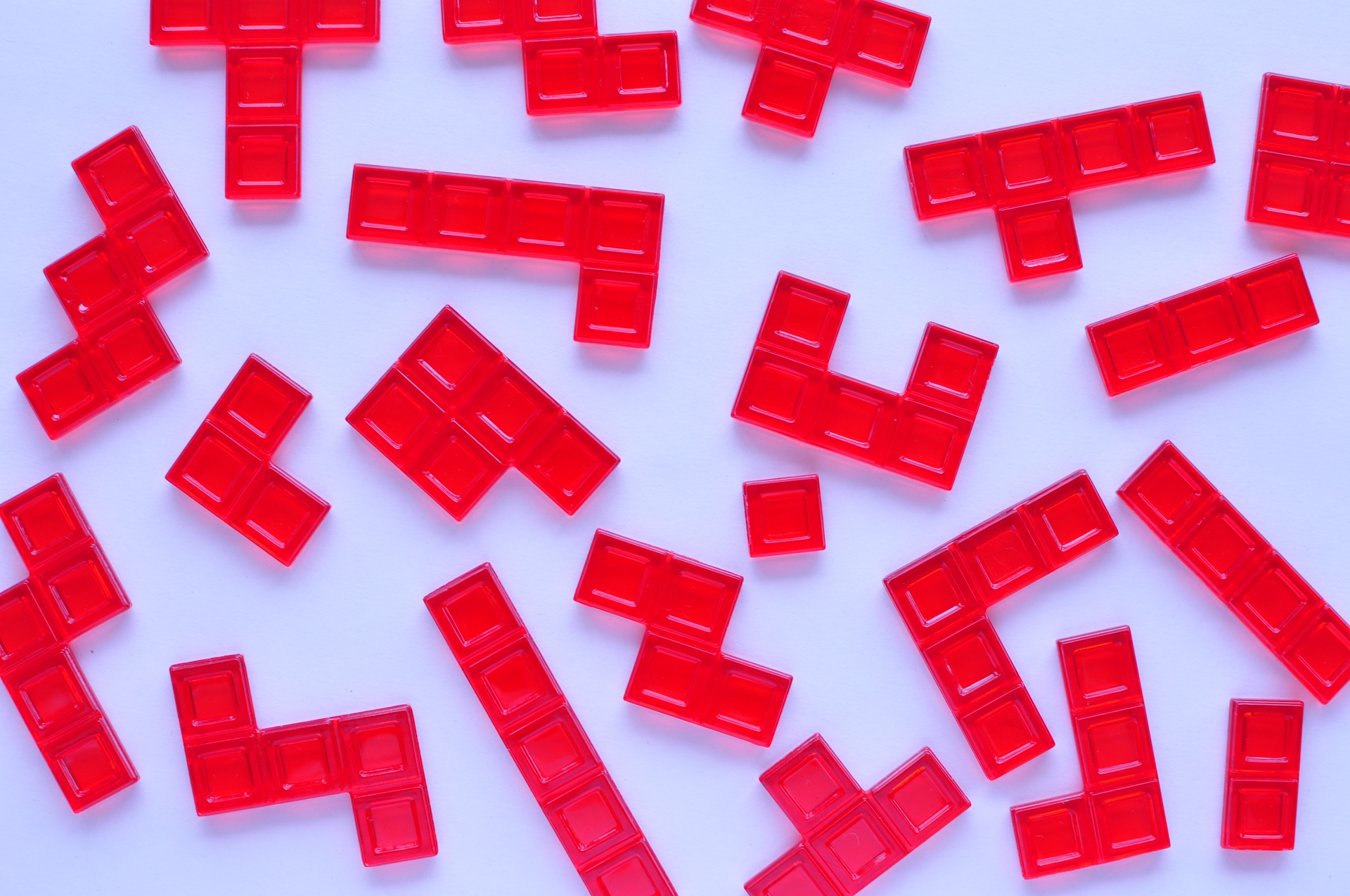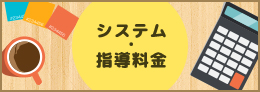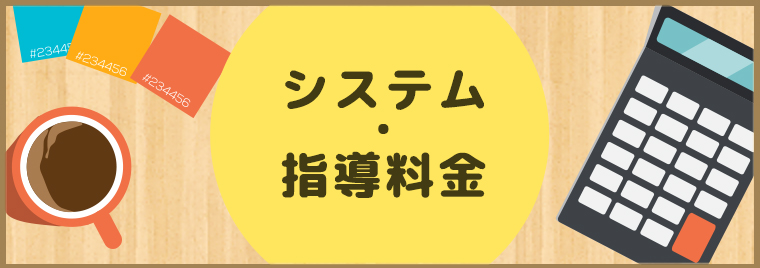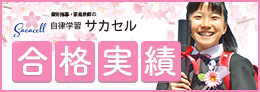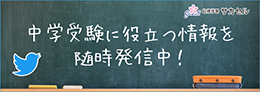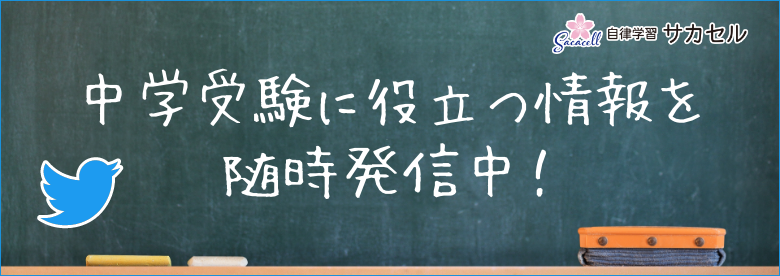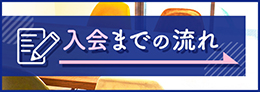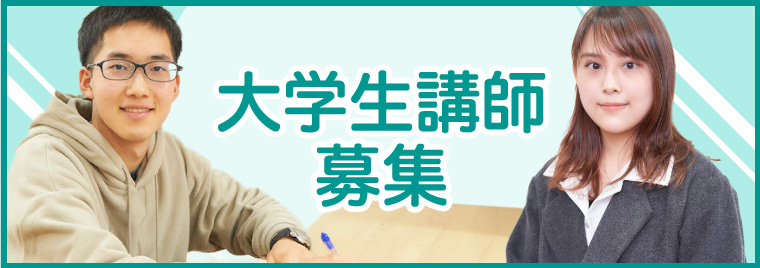世田谷学園中。
以前はスポーツの名門校で有名な学校でしたが、1980年代に進学校へとシフト。
東大などの国公立大学だけでなく、医学部への受験を積極的に行う背景があり、
2021年度に理数コースを設置。
さらなる進学実績の伸びを期待される学校です。
◆各種データ
合格者平均 53.9点
受験者平均 43.7点
想定合格ライン 50点
合格者最低点 184/300点
◆出題形式
試験時間50分 100点満点
◆大問1題構成
大問1 論説文 小問数42問
◆問題の種類(2020年度)
・記述 10%
・選択肢 60%
・抜き出し 10%
・漢字 20%
という割合になっています。
2019年度から大問3題構成から1題構成となり、大きく傾向が変わりました。
後半に長文の記述を複数問書かせる点、漢字などの設問が多い点も特徴でしょう。
比較的、「努力が報われやすい形式」と言えると思います。
ここからは2020年度の世田谷学園中①の出題を通して、どのような戦術で取り組んでいけばよいかを検討していきたいと思います。
今回使用する指標
○…合格には確実に取れてほしい問題
△…合格の勝負所・差がつく問題
×…落としても合否には大きく影響しない問題
解答例はこちら
大問1 論説文 岡田美智男「〈弱いロボット〉の思考 わたし・身体・コミュニケーション」
問1漢字 ○
10問ほど出題されます。
送りがなまで聞かれるタイプの出題ではないので、全問正解を狙いたいところです。
「所作」のみ、少々難しかったかもしれません。
問2語彙 ○
設問だけで考えず、文の中でどういう意味で使われているのかを検討するのが良いでしょう。
問3接続語 ○
選択肢を全て使い切るタイプの問題。
選択肢の「余り」が出ないタイプの問題ですので、慎重に検討し、全問正解したいところです。
問4表現の穴埋め ○
用意された語群をヒントに、適切な表現を本文に当てはめる問題です。
こちらも語群の「余り」が出ないタイプの問題ですので、全問正解を狙いたいところです。
問5選択肢 ○
お掃除ロボット<ルンル>は「これまでの家電」とどのような点において違うのか答える問題です。
同じ段落にある「ロボットの動きを思わず追いかけてしまう」「いたずらをしてみたくなる」「先回り~紙袋を拾い上げ、~乱雑なケーブル類を束ねていたりする」などをヒントにします。
これらを言い換えているイが正解です。
問6選択肢 ○
「主客転倒」とはどういうことか答える問題です。
「主」は、主人・主観など、「客」は、客人・客観などで置き換えて、反対の関係と捉えられるかどうかが重要ではありますが、それが完全にわかっていなくても、
「~これでは主客転倒ということになってしまう~」
のこれの中身をチェックして、
「お掃除ロボットのために、人間が先回りして紙袋を拾い上げたり、乱雑なケーブルを束ねていたりすること」
が拾えれば、【掃除が目的のロボットのために、ロボットの持ち主である人間が先回りして掃除の手伝いをしていること】が読み取れると思います。
答えはアです。
問7選択肢 ○
「なぜお掃除ロボット<ルンル>は筆者にとって不思議な存在だと言えるのか」を答える問題です。
傍線部③と同じ段落にある
「ロボットの<弱さ>は、わたしたちにお掃除に参加する余地を残してくれている」
「一緒に掃除をするという共同性~を引き出している」「達成感をも与えてくれる」
という内容の言い換えを選ぶ問題ですが、選択肢の抽象度が高いので、×ポイントを探す方が解きやすいかもしれません。
正解はオ。
ア「高度な作業」
イ「同情を買う」
ウ「最終的には部屋の掃除を完了」
エ「機能的な欠陥」など、他は全体がマイナスの印象になっています。
問8選択肢 △
【 あ 】にあてはまる内容を答える問題です。
まず、【 あ 】の段落を見て、
「【 あ 】ことを『帰属させる』と表現することがある」「これは『せっかくだから、なにかのせいにしてしまおう』~」
に注目します。【 あ 】と「帰属させる」は関係がありそうですね。
次に、【 あ 】の前の段落に、
「~フラフラではないのかと、その原因を夏の暑さに求めはじめた」
に注目します。
「蟻がフラフラと動く原因を夏の暑さに求める」ことがわかりますね。
また、【 あ 】の後の段落に
「ここでリュウイしたいのは~帰属させやすい」
とあり、「ここ」は【 あ 】の段落を指し、同じ文の中に「帰属させやすい」とあるので、【 あ 】と関係があることがわかります。
【『なぜフラフラなのか』に対して、『この蟻はきっとお腹が空いているのではないのか』とは、すなわち蟻の内部にその原因を求めている】というのが続きを読むと見つかります。
この内容を言い換えているものを選び、答えはエとなります。
【 あ 】の段落だけ読むと引っかかるので、一応△としています。
問9穴埋め ○
「【 い 】と【 い 】に入る【対となる言葉】」を入れる問題です。
い を含む一文に注目すると、
「~私たちは目の前にある対象の振る舞いを引き起こした要因を探るとき、その対象の【 い 】側で起こっていることに帰属させやすい~」
とあります。その直後に
「『なぜフラフラなのか』に対して、『この蟻はきっとお腹が空いているのではないのか』とは、すなわち蟻の内部にその原因を求めている」
とあります。
各色の内容がそれぞれの内容に対応していることから、
【 い 】は「内」。
【 う 】は内の反対なので「外」になります。
【 い 】の周辺だけ読めば答えが載っている問題ですので、○としています。
問10抜き出し △
「鳥瞰的な視点には盲点もともなうようなのだ」
の盲点の内容を説明している一文を答える問題です。
傍線部④は段落の最後にあるので、傍線部④の次の段落に注目します。
すると、
「先に触れたように~。あるいは、~求めようとする。」
とあります。
先に触れたように~も、 ~求めようとする。 もどちらも蟻に関わる具体例で、「一文」に絞り込むことはできません。
~求めようとする。の後の文は【とりあえず動くものに~わたしたちの帰属傾向といえる。】とあり、前の2つの文をまとめた内容となっています。
ですので、【とりあえず】が正解となります。
具体と抽象の読み分けが出来ていないと答えが1つに絞れないので、△としています。
問11抜き出し △~×
「行為者としてのロボットの視点に立つならば、目の前に迫りくる椅子や壁を避けるようにして動いていたら、結果として部屋のなかをまんべんなく掃除してしまっただけといえる」
という視点は、お掃除ロボットの働きぶりを生み出す要因をどのように考えたときに生じるか について答える問題です。
傍線部⑤を含む一文に「しかし」とあるので、その前を見ると、
「わたしたちの視点からは、~その働きぶりを生み出す要因をいつのまにかロボット内部の働きに帰属させていたのだ」
とあります。
傍線部⑤ と 「わたしたちの視点からは、~その働きぶりを生み出す要因をいつのまにかロボット内部の働きに帰属させていたのだ」は逆の関係です。
つまり、ロボット内部の逆、「ロボット外部」の内容を探します。
わたしたちの視点~の段落の1つ前に、「こうした観点から~」が見つかりますので、もう1つ前の段落をチェックします。
【もちろん、蟻の足跡の複雑さを、~環境の複雑さだけで説明するには無理があるだろう。】とあります。
ここから、【環境の複雑さ】が答えとなりますが、「6字」でそれっぽい内容を探して当てた子も多そうです。
△~×としています。
問12i選択肢 ○
「学生がどのような意味でLINEでの会話を蟻の足跡にたとえたか」について答える問題です。
傍線部⑥のセリフの中に「このやりとり」とあるので、「このやりとり」の中身を拾って、言い換えたものを選びます。
答えはウになります。
問12ii記述 △~×
「LINEでの会話を『蟻の足跡』にたとえたとき、会話の中の一つひとつのアイディアはどのような要因によって生じた」と考えられるか、について答える問題です。
設問に「蟻の足跡」「要因」とあるので、「もちろん、」から始まる段落に注目します。
問11でチェックした段落ですね。
「蟻の個体としての機能やそれを取り巻く環境のどちらか一方に要因があるというより、その二つのあいだにわかち持たれたものともいえるのだ。」
ここで出てくる蟻の話を、「会話の中のアイディア」の例に置き換えます。
【学生個人の発言と、それを取り巻く人達の発言のあいだに、わかち持たれて】としました。
受験者平均などから見ると、かなり難しく感じられた問題なのだろうと感じます。
問13選択肢 △
「はたして、このことをかしこい振る舞いととらえてしまっていいものなのか」に対する返答を答える問題です。
二重傍線部Xから、筆者は「このことをかしこい振る舞い」とはとらえていません。
ロボットが不完全だから、人間が手助けをして、結果掃除が完了する話は問5・6・7あたりから拾うことが出来ます。
「本文の全体を踏まえた返答」ということは、他の問で答えた内容と整合性が取れていないといけないわけです。
答えはエになります。
問14i記述 ×
筆者の研究室で開発されたロボットの3つの特徴から、このロボットの「<不完結さ>や<弱さ>」を明らかにした上で、それがもつ「可能性」を説明する問題です。
問13の内容と関係のある問題となっています。
「ロボットが不完全だから、人間が手助けをして、結果掃除が完了する」
という話と、こちらの条件にあてはまる特徴を比べて、整合性が取れるようにします。
問13が取れていないと、書くのは難しいでしょう。
問14ii記述 ×
「ロボットやAIが進化して人間の仕事が大幅に減少し、経済活動に多大な影響を及ぼすことが懸念される時代の中で、ロボットの<不完全さ>や<弱さ>はどのような状況をもたらし、人との関わりの中でどのような役割を果たすことが期待できると考えられるか」、自分の考えを書く問題です。
これも、問13・問14iが答えられていないと解答は難しいでしょう。
「ロボットが不完全だから、人間が手助けをして、結果○○○○○○」の○○○○○○に何が入るか検討します。
私は「人間がロボットをフォローしなければならない状況」から、「新社会人や学生向けに向けた教育の役割」としましたが、問13・問14iと連動して解かなければならないこの年度だと、難しかったでしょう。
問15正誤問題 △
本文と見比べて「当てたい問題」ですが、時間がギリギリだと苦しいかもしれません。
問14のiもiiも、学校側が気合を入れて作った問題なのでしょうが、合格者平均・受験者平均が50点近辺になっていることから、難しすぎて手が出ない子が多かったのではないかと考えられます。
そういう意味で言うと、「問9まででいかに丁寧に解いて点数を作るか」が合否の分かれ目となりましたが、裏を返せば「記述でほとんど差のつかない問題」と言え、「ミスをしない戦い」となってしまい、本来学校の先生型が意図したであろう「記述で力の差を測る」ことができていない年度だったと言えるでしょう。
形式を変えて数年ということもあり、こういう年度も時々あると思います。
どんな形であれ、自分の実力をしっかり出していかないといけないですね。
にほんブログ村にも参加しています。ぜひ下のバナーをワンクリックで応援もお願いします!

.jpg)