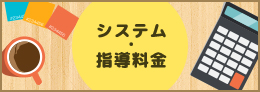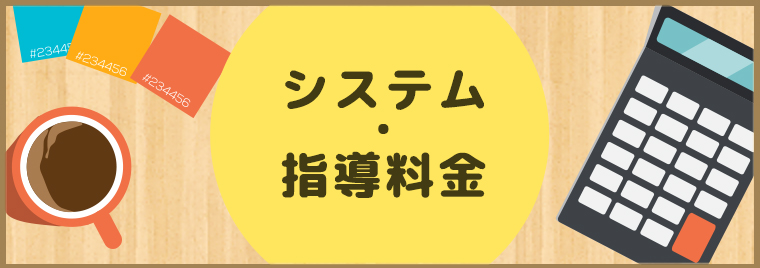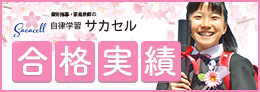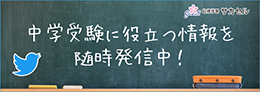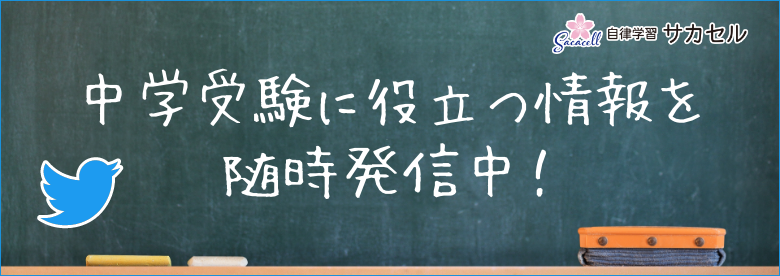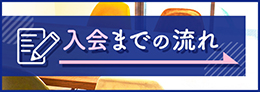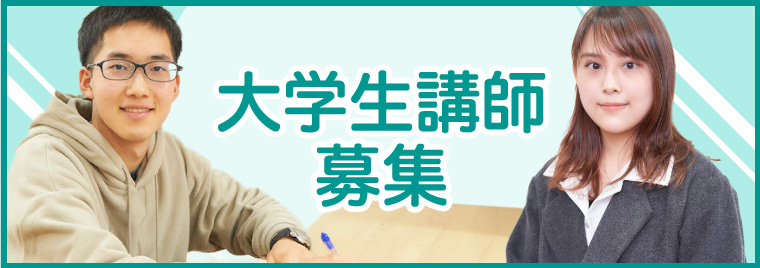2022年3月18日投稿
2024年3月27日更新
6年生になって、怒涛のテスト続きですね。クラス昇降もあり、内容的にも重要単元ばかりの4月マンスリー!燃焼・電流・太陽・月はそれぞれ難しさのタイプが違います。得意単元を作って稼ぐこと+苦手単元は確実に取れる問題をできるだけ増やしておくことをおススメします。
【各単元のポイント】
各単元のポイントをまとめたので参考にしてみてください。
重要度は以下です。
◎:絶対!
〇:テスト対策としてここまで解いておくとよい
△:できれば取り組んでおきたい
無印:余裕があれば
630-06 燃焼
燃焼は原理が難しく、その理解の深さをあの手この手で確認してくる問題が多く出題されます。なるべく正確に理解することを意識しましょう。
・燃焼とは?
◎燃焼=燃えるものが酸素と結びつく ということを理解し、燃えてできる物質を覚えましょう。
炭素+酸素→二酸化炭素
水素+酸素→水 ※
銅+酸素→酸化銅
マグネシウム+酸素→酸化マグネシウム
燃える=酸化〇〇になる、ともいえますね。
※水素が燃えてできる物質は酸化水素…といいたいところですが、水というとても身近な物質なので「水」と呼びます。
・ろうそくの燃焼(確認問題[1][2])
◎ろうそくの炎の各部の名称、特徴、その理由を覚えましょう。(P3右)
◎ろうそくの炎にガラス管などを入れたときの変化を覚えましょう。
湿らせた割りばし→外炎でこげる
ガラス棒→内炎ですすがつく
ガラス管→炎心で白い煙、内炎で黒い煙(P3右下)
◎ろうそくが燃えて出来る物質を覚えましょう。
◎ろうそくは炭素と水素で出来ているので燃えると二酸化炭素と水が出来ます。
→燃えて出来た物質は空気中に逃げるので燃えた後は軽くなります。
◎燃えてできた物質を確かめる方法も覚えておきましょう。(表紙上中央)
二酸化炭素→石灰水が白くにごる
水→塩化コバルト紙が青→赤
〇ろうそくは気体になってから燃えていることを理解しましょう。
ろうそくを吹き消す場合、炎心にあるろうの気体(燃えるもの)を吹き飛ばすことにより火が消えます。
・金属の燃焼(確認問題[3][4][6][7])
〇銅、鉄の燃える前の色、燃えた後にできる物質の色を覚えましょう。(P5左)
◎金属は燃やすと酸素と結びつき重くなることを理解しましょう。
◎金属の燃焼の計算問題を解けるようにしておきましょう。
ことばの式を書き、その下に重さを書き加えられるようにしていくとよいです。
銅+酸素→酸化銅
4g 1g 5g
〇金属の燃焼の応用パターンをマスターしましょう。
確認問題[7]にまとまっています。
(4)不完全燃焼パターン…結びつく酸素の重さに注目して解きます。
(5)2種類の金属の合計の重さが出ているパターン…つるかめ算で解く、または消去算で解きます。
つるかめ算で解く場合ははじめに1gあたりの値(面積図の縦の値)を出さないと解けないことを確認しておいてください。
〈消去算での解き方〉
例 銅とマグネシウムの合計13.5g、燃焼後の合計20gのとき、はじめにあったマグネシウムは何gですか。
銅④+酸素①=酸化銅⑤
マグネシウム3⃣+酸素2⃣=酸化マグネシウム5⃣
④+3⃣=13.5
⑤+5⃣=20
これを解いて銅①=1.5g、マグネシウム1⃣=2.5g
はじめにあったマグネシウムは3⃣=7.5g
・木の蒸し焼き(確認問題[9][11])
〇蒸し焼きとはどういうことか理解しましょう。(P4右)
〇割りばしを蒸し焼きにしたときにできる物質を覚えましょう。(P4右)
・金属のさび(確認問題[8])
〇さびとは何か理解し、鉄がさびやすい条件を選べるようにしましょう。(P5右)
・引っかかりやすい問題(確認問題[5]ほか)
〇銅や鉄を燃やした集気びんに石灰水を入れると…
→変化なし
二酸化炭素が発生していないので変化しません。
ものが燃えると絶対に二酸化炭素が発生する、と思っている生徒がかなりいます。正確に理解しましょう!
△ろうそくを燃やしたときに出来る物質は?
→二酸化炭素と水
…物質名なので、水蒸気ではなく「水」と答えるのがよいです。
△ろうそくは酸素が少なくなると消えるので、火が消えた後にも酸素は残っています。
※酸素が17%くらいになると消えます。
△酸素50%二酸化炭素50%が入った集気びんに火のついたろうそくを入れると…
→はげしく燃える
酸素が空気中(21%)より多いのではげしく燃えます。二酸化炭素は特に何もしません。燃焼が酸素によって起こっていることを理解しているか確認する問題です。二酸化炭素は悪者、火を消すはたらきがあるのでは?といった間違った理解をしているとはじかれます。
◎630-06 確認問題[1]~[5]
デイリーステップ[2][4][6]
ポイントチェック[5]
〇630-06 確認問題[6][7][9][10][11]
△630-06 確認問題[8][12]
発展問題[1]
※青字はマンスリー過去問です。
H63-01 電気のはたらき
今回初めて電気抵抗を使った電流の数値化が登場しています。ただ、マンスリーでは誘導問題になっていることが多く、電気抵抗の考え方に慣れていなくても解けるようになっていたりします。逆に誘導に乗るのが苦手、という生徒は一人で解けるように抵抗の考え方をしっかりマスターしておくことが重要になります。
・電流計(確認問題[1])
◎電流計の使い方を覚えましょう。(P4右下)
・電流の基本回路(確認問題[2][3])
5年生で習った電流の復習です。ここはとても重要ですので、どのクラスの生徒も絶対に出来るようにしましょう。
◎電流を数値化できるようにしましょう。(P5)
テキストでは、電流の値は「1」や「1/2」などで表す問題が多いですが、テストでは1=120mAなどとなっていることが多いので、必ず確認しましょう。また、回路のどこに電流計があるのか確認することも忘れずに!
ここが不確実な場合はポイントチェック[3]も使ってしっかり固めましょう。
・特殊な回路(確認問題[4])
◎ショートと電流が流れない回路の違いをはっきりさせておきましょう。(P4)
ショート→抵抗のない道の方を選んで強い電流が流れる
電流が流れない→向きが決まらないので流れない
・電気抵抗の考え方 (確認[7][8])
◎抵抗を求めてからでないと電流の値が求められないパターンをマスターしましょう。(P3右)
◎まず、抵抗の考え方をしっかり理解し、抵抗を使って電流の値を求められるようにしましょう。
◎「5年生までの考え方の方が楽なもの」「抵抗を使わないと値が求められないもの」を判断できるようにしましょう。
◎H63-01 確認問題[1]~[4],[7]
デイリーステップ[2][4][6
ポイントチェック[5]
〇H63-01 確認問題[5][6][8][12][13]
△H63-01 確認問題[11]
発展問題[1]
※青字はマンスリー過去問です。
H63-02 太陽
習ったときは難しく感じないのに、問題を解こうとすると難しい単元です。なぜなら問われていることがどこから分かるのか、着眼点が見つけにくいからです。
後半に判断材料をまとめたので参考にしてみてください。
・公転図・天球図・日影曲線(確認問題[1][2][4][5][6][7][11][12])
◎地球の公転図・天球図・日影曲線を見て、方位・動く向き・季節を判断できるようにしましょう。
影の動きは間違いやすいので注意が必要です。
太陽が東→南→西 と動くので
影は西→北→東 と動いていきます。
◎春分・夏至・秋分・冬至は3の倍数月であることを覚えておきましょう。
◎各季節によって日の出・日の入りの位置が変わることを理解し、季節⇔日の出・日の入りの位置を対応させられるようにしましょう。(確認問題[8])
・緯度・経度(確認問題[3][9][10][11][12])
◎緯度と経度を理解しましょう。(P4左、P5左)
緯度:赤道からの角度。北緯は北にいくほど大きくなります。北極は北緯90°です。
経度:イギリスの旧グリニッジ天文台からの角度。東にいくほど東経が大きくなります。
◎日の出の時刻と日の入りの時刻から昼の長さと南中時刻を求められるようにしましょう。
◎南中時刻⇔経度の計算が出来るようにしましょう。(P4左下)
南中時刻は東ほど早いことをしっかり理解してください。
◎南中高度の式を覚えましょう。P5右上
◎日本国内では南中高度は南ほど高いことを知っておきましょう。
◎夏は南中高度が高く、冬は南中高度が低いことを理解しておきましょう。
・2つ以上の条件を組み合わせて考える(確認[6][9][10][11][12])
季節や場所を複数の条件から絞り込んでいく問題が、太陽の典型的な応用問題になります。
〈場所を判断するのに使うポイント〉
〇東西(経度)の判断→南中時刻から
南中時刻は東ほど早いこと、東経135度の明石市では12:00に南中することが重要です。
〇南北(緯度)の判断→南中高度または昼の長さから
南中高度は南ほど高いことと
夏は北ほど昼が長い(冬は南ほど昼が長い/春分秋分はどこでも昼の長さ同じ=12時間)ことがよく登場します。
※この手の問題で日の出が早い方が東、と判断するのは危険です。春や秋なら問題ありませんが、夏は北ほど昼が長いので、同じ経度でも北の方が日の出が早くなるからです。
〈季節を判断するのに使うポイント〉
〇昼の長さ
12時間より長ければ夏寄り、短ければ冬寄りです。
〇昼の長さの変化
長くなっていれば夏に向かっている/短くなっていれば冬に向かっている
と判断できます。
※日の出と日の入りの時刻は2日分以上データがあり、昼の長さの変化が分かるようになっています。
〇南中高度
春分秋分(90―35=55)より高い場合は夏寄り、低い場合は冬寄りと判断できます。
※北緯35度の場合
〇影の長さ
短いほど太陽高度が高い→夏寄り です。
〇気温
夏は暑い、冬は寒いは当たり前ですが、3月と9月でどちらの気温が高いか?は小学生には難問です。
9月は夏の後で地面に熱が残っているので気温が高いことを理解しておきましょう。
このように、与えられている情報から何が分かるのかをしっかり把握しておくことが重要です。
◎H63-02 確認問題[1][2][3][5]
デイリーステップ[2][4][6]
ポイントチェック[4]
〇H63-02 確認問題[4][6][9][10][11][12]
△H63-02 確認問題[7][8]
※青字はマンスリー過去問です。
H63-03 月
とにかく月の公転図を使いこなせるようにしましょう。今後の天体の応用問題に対応するためにも、今のうちに図を使いこなして考えられるようになることが重要です。
・月の公転図(確認問題[1][2][3][4][5][6][7][8][10][11][12])
◎公転図から月の形を判断できるようにしましょう。
◎公転図を使って時刻と方位から月の形を判断できるようにしましょう。
例 日の出頃、南西の空に見える月
- 地球に時刻をかき込みます。
- 指定された時刻のところで方位をかきこんで判断します。
※日の出→6時です。
※時刻の位置で十字をかくこと、北極のある方が北、がポイントです。
△月の傾きを考えられるようにするとさらによいでしょう。
〇月が満ち欠けするのにかかる日数を求められるようにしましょう。
例 上弦の月から新月までは何日かかりますか。
一周約30日なので、1/4は7.5日、を覚えておくとよいでしょう。まわる向きにも注意が必要です。
上弦の月から新月までは3/4ですので
7.5×3=22.5日くらいです。
サピックスのテストではこのように色々なところに引っかかるポイントが作られています。
確認問題では公転図が示されていない問題もありますが、マンスリーでは必ず図が載っていますので、図を使いこなしましょう。
・月の出・月の入りの表(確認問題[5][11][12])
〇月の出/月の入りの時刻の表から月の形を判断できるようにしましょう。
例 月の出 9:00 月の入り 21:00
〈解き方1〉
- 月の出の時刻(9:00)のところに方位をかき込みます。
- 月の出は東なので、この時刻(9:00)に東にある月、ということになります。
三日月ですね。
〈解き方2〉
南中時刻を求めて解く方法もあります。
- 月の出9:00、月の入り21:00なので南中時刻は
(9:00+21:00)÷2=15:00
- 15:00で方位をかき、南にある月を探せばOK!
△月の出/月の入りの時刻の表から月が地平線上に出ていた時間を求められるようにしましょう。
例 次の表から○日に出た月が地平線上に出ていた時間を求めなさい。
○日 月の出12:20 月の入り0:10
翌日 月の出13:05 月の入り0:58
0:10→24:10 24:10-12:20としてはいけません。
この表の○日に出た月は○日の0:10に沈むことは不可能です。○日に出た月は地平線上に出ている間に翌日になり、翌日の0:58に沈んだ、ということが表されているのです。
よって 24:58-12:20 で求めます。
◎H63-03 確認問題[1][2][4][5][6]
デイリーステップ[2][4][6]
ポイントチェック[4]
〇H63-03 確認問題[3][7][8][11][12]
△H63-03 確認問題[9][10
※青字はマンスリー過去問です。
【直前対策】
直前にする対策について、レベル別に少しまとめておきます。
時間があまり取れないようでしたら、テキストの次の回のデイリーチェックとデイリーステップ[1]がおススメです。
青字はマンスリーの過去問です。
偏差値~42 ◎H63-01~630-07 デイリーステップ[1]
〇630-06~H63-03 デイリーステップ[6](大問1対策)
〇630-06~H63-03 デイリーステップ[2][4]
42~54 ◎H63-01~630-07 デイリーチェック、デイリーステップ[1]
〇630-06~H63-03 デイリーステップ[6](大問1対策)
〇630-06 確認問題[11]
〇H63-01 確認問題[12][13]
〇H63-02 確認問題[11][12]
〇H63-03 確認問題[11][12]
△630-06~H63-03 各単元のポイントで◎の問題(デイリーステップはカット可)
55~ ◎H63-01~630-07 デイリーチェック、デイリーステップ[1]
〇630-06~H63-03 デイリーステップ[6](大問1対策)
◎630-06 確認問題[11]
◎H63-01 確認問題[12][13]
◎H63-02 確認問題[11][12]
◎H63-03 確認問題[11][12]
〇630-06~H63-03で解いた問題の復習
SAPIX新6年4月マンスリーの各教科の解説はこちらをご覧ください!
SAPIX新6年4月マンスリーで押さえるべきポイント!算数編
SAPIX新6年4月マンスリーで押さえるべきポイント!国語編
SAPIX新6年4月マンスリーで押さえるべきポイント!理科編
SAPIX新6年4月マンスリーで押さえるべきポイント!社会編
SAPIXに関して、より詳しく知りたい方はこちらをご覧ください!
塾選びから合格(または転塾)までSAPIX完全解説
にほんブログ村にも参加しています。ぜひ下のバナーをワンクリックで応援もお願いします!



.jpg)