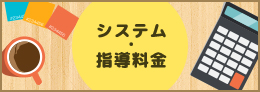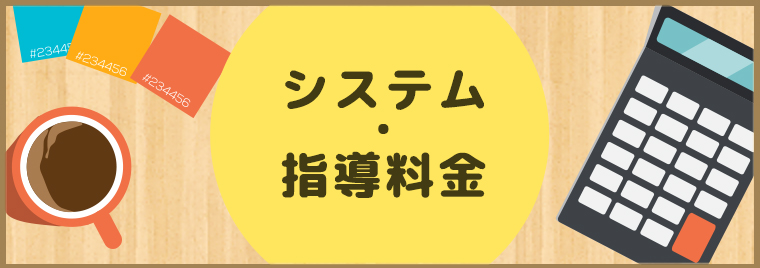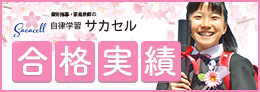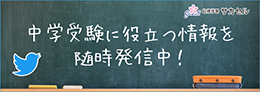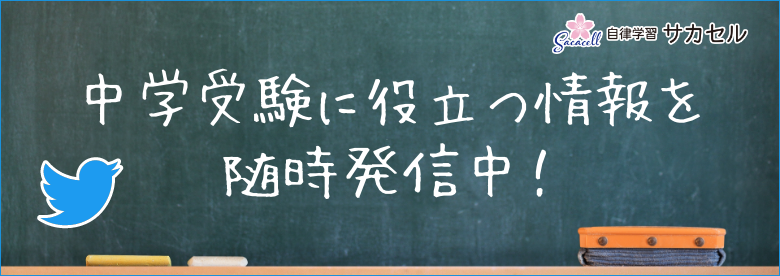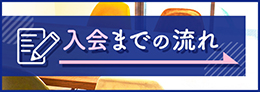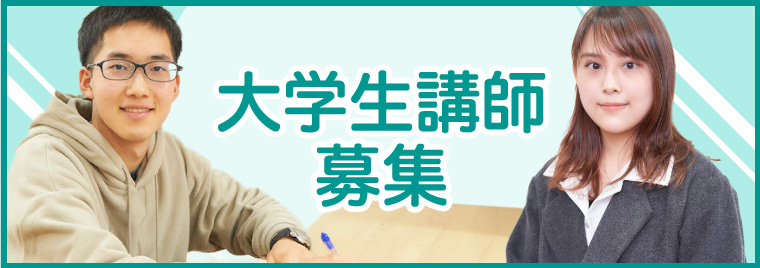女子御三家の一角、女子学院。
制服の着用義務が無いなど自由な校風で知られる一方で、大学合格実績は女子校トップクラス。
かつては宿題量も多くはなかった学習面に関しては近年、宿題の量などの学習量が増えているそうで、面倒見も向上しているそうです。
また学問にとどまらず、文化や芸術分野まで各界に優秀なOGを輩出していることでも有名です。
入試問題も独特です。
算国理社の4科目すべて制限時間40分で100点満点の配点は、算国を重視する中学受験では珍しいパターンです。
4科目バランス良く学習してきた生徒が欲しいというメッセージでしょう。
各科目の出題内容も、見たことのないタイプの問題をその場でじっくり考える力よりも、今までに学習してきた内容を手際よく処理していく力が問われる構成です。
算数に関しては例年20~30問の小問(実質は20問前後)を40分で処理しなければならない、スピード・正確さ・知識が高度に求められる試験と言えるでしょう。
頻出分野は「平面図形」「速さと比」「和と差や比と割合の文章題」が挙げられます。
いずれの分野も、比を活用した典型解法への習熟が問われる、選抜試験としては適切な難度が設定されています。
合格ラインは発表されていないものの例年ならば70点以上が必要になってくることは確実でしょう。
前年の2017年は非常に易しかった一方、難易度の上下は珍しくない学校です。
70点でOK!と決めてかからないよう、気を付けましょう。
では、ここからは2018年の出題に注目してみましょう。
今年は大問7題、小問は実質18題という近年では標準的な出題量となりました。
出題内容も女子学院の頻出テーマが並んだと言えそうです。
例年だと数問みられる高難度の問題も配置されなかったので、合格ラインはやや高めであると想定されます。
以下、小問ごとに内容を確認し、合格にはどのような得点戦略が必要か考えていってみましょう。
〇:女子学院合格のため必ず正解したい問題
△:合否の分かれ目になる問題
×:間違えても合否には影響しない問題
大問1
(1) 〇
普通の計算問題です。
分数で処理し、確実に正解しましょう。
(2) 〇 〇 〇
女子学院頻出の角度の問題です。
様々な二等辺三角形を見つけましょう。
(3) 〇 〇
基本的な損益の問題です。
100+82=182円が25%の利益にあたります。
(4) 〇 〇
流水算の典型題です。
出会いの場合、流速は打ち消しあうことを利用しましょう。
(5) △ △
意外と気づきにくい平面図形の問題です。
補助線を引いて、底辺が60cmで高さが150cmの平行四辺形を作ることが出来れば、そこから三角形を2つ除くだけです。
ABの長さはオマケですね。
大問2
(1) 〇
底面積が1辺12cmの正方形か半径5cmの円で、高さの和が9cm、体積が935.75㎤になるよう、つるかめ算で処理しましょう。
女子学院志望者なら手際よく処理したい問題です。
(2) 〇
上下と側面積に分けて考えます。
こちらも多少面倒ではあるものの、確実に正解したい問題です。
大問3 △
「3日より多く4日以下」という処理が意外に難しい仕事算です。
A1台が1日に1の仕事とすると全体の仕事量は33
B1台が1日に①の仕事とすると
3×3+②×3=33 だと①=4
3×4+②×4=33 だと①=21/8
33÷4=8.25日 ⇒ 9日以上
33÷21/8=12.5…日 ⇒13日以下
と考えられます。
大問4
(1) 〇
題意の確認問題です。
間違えるわけには行きません。
(2) 〇
赤が2=約数が2個=素数と言い換えましょう。
2は唯一の偶数の素数です。
(3) △
素因数分解して約数の個数を求める方法を知っているなら易しいです。
2×3×□(素数)で40以下のものは□=5の時の30しかありません。
(4) 〇
約数が3つになる数は、同じ素数をかけた平方数です。
この問題は良い題材なので、算数科講師としてはもう少し掘り下げてほしいところでした。
大問5 △
「先生が必ず2人乗る」ことから、55人乗りのバスに乗れる生徒は53人、40人乗りのバスに乗れる生徒は38人と考えましょう。
53×□-30 = 38×(□+2)+29 と置き換えられます。
この後の式の処理を苦手とする中学受験生は多いので、差がつきやすい問題と言えるでしょう。
大問6 〇 〇
空きビン交換の問題は中学受験では頻出です。
今回は、どの塾のテキストにも掲載されていいる典型題そのままの出題だったので、確実に正解したい問題です。
大問7
(1) 〇
基本問題です。
面積図や天秤で確実に正解しましょう。
(2) △ △ △
やや処理量が多いものの、作業自体は基本通りです。
1つ1つ、面積図や天秤で処理しましょう。
流れ図に整理しなくても正解できる問題です。
このように問題を見渡しても、×にあたる問題はありません。
大問1が実質5問、大問2が2問、大問3が実質1問、大問4が実質4問、大問5が実質1問、大問6が実質2問、大問7が実質3問で、合計で18問。
〇が12問なので11/12、△が6問なので3/6、あわせて14/18=約78点が合格ラインと言えそうです。
来年以降に女子学院を目指す生徒は、このテストで80点以上を確実にとれるように典型問題の知識を身につけ、その上で過去問を利用してのスピード演習を重ねましょう。
分野別の学習としては、「和と差、比と割合の文章題」「速さと比」に力を入れましょう、こちらは過去問だけではなく、塾での問題集による学習も効果的です。
平面図形に関しては、過去問をさかのぼることが最も良いでしょう。
古い年度は40分のセットで解くのではなく、分野ごとに取り組んでみることも効果的ですよ。
是非とも盤石の基礎力と最高レベルの処理速度を手に入れましょう!
女子学院なら必ずや楽しい学校生活を送れることでしょう。