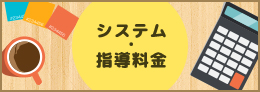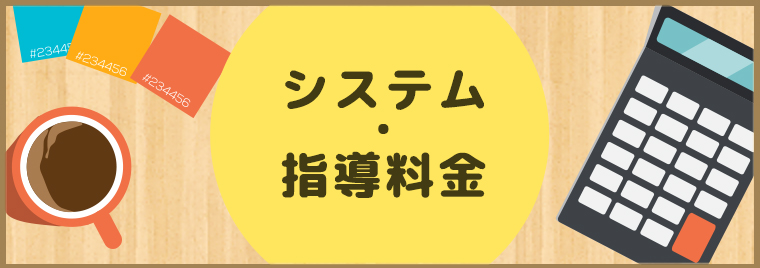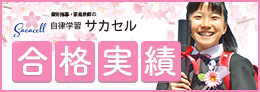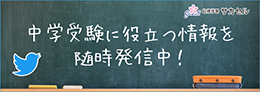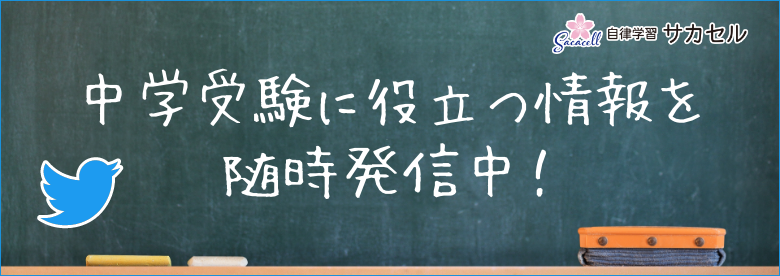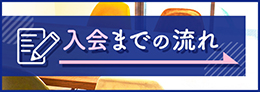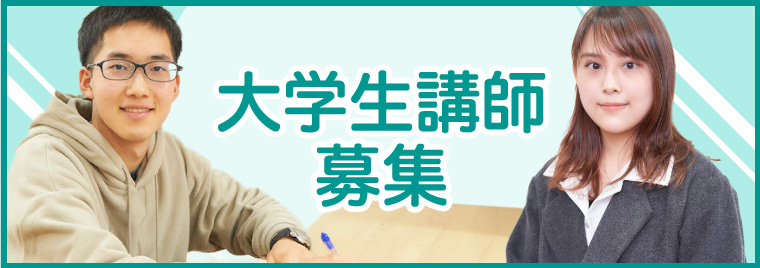11回〜14回が範囲となっている組分けテスト。
随筆文が初登場となっています。
【構成(毎度同じなので再掲となります)】
50分 配点・出題形式は一例です。
大問1 漢字10点 書き取り10問
大問2 知識10点 選択肢7問
語彙7点 選択肢3問 書き取り2問
大問3 物語文・小説文66点 選択肢5問、抜き出し4問、記述2問
大問4 説明文・論説文57点 選択肢3問、抜き出し4問、記述1問
まず、設問の分量が多いです。
50分の中で40問程度の設問に取り組まなければなりません。
四谷大塚主催の模試では、「文章を読む時間がなくて、文章を読まずに解いた。」というコメントが出ることも少なくないです。
読むのに時間がかかる場合、解く設問に優先順位をつけなければならないでしょう。
記述問題に関しては、90字など文字数指定が厳しい問題であるにも関わらず、5~8点など低めの配点がつけられていることも。
入試問題において、取り組むべき優先順位は 選択肢>記述>抜き出し となることが多いです。
本番で「記述を書かない」ことは致命傷になるケースが多いのですが……。
「四谷大塚の模試で点数を取る」ということに主眼を置く場合、記述問題の優先順位を下げた方が点数が取れるということもあり得ます。
どうしてもテストが解き終わらないなど、「設問を一問でも多く解くことを目指さなければいけない」場合は知っておいてもよいかもしれません。
次に、問われる内容が多岐に渡るということです。
中学入試は、傍線部の内容説明・理由を中心に設問が作成されることが多いです。
四谷大塚の模試は、傍線の表現の意味、場面・意味段落分け、指示語の中身のチェック、▶︎マークの入った範囲の中で気持ちの変化を問うものなど、様々な内容が聞かれます。
その時、その文章でのみ当てはまる内容でなく、「時間にあたる表現があったら、文章を読んでいる最中に◯をつけておく」など、どんな動きをして答えを探すのか、自分なりに取り組み方をある程度決めておく必要があると思います。
最後に、読解の抜き出し問題が多いです。
それに伴って、選択肢問題は少なめです。
「本当は記述で出題したい」問題を「抜き出し」形式に置き換えて聞いているという印象があります。
「設問で聞かれている内容」に散りばめられているヒントが、「文章のどのあたりにあったのか」が見つけられるかどうかで正解するかどうかが決まることが多いです。
本文に線を引いたり、マークをつけたりなどして、「本文のどのあたりにどの話があったのか」を一読後、少しでもおさえられる動きが取れると良いでしょう。
【対策(毎度同じなので再掲となります)】
漢字:漢字とことばの総合回 「総合復習問題」
知識:予習シリーズの総合回 「大問3以降の知識問題」
語彙:漢字とことばの総合回 「第◯回 総合」を解く
読解:演習問題集の総合回、予習シリーズの総合回大問1・2
基本的に上記の内容に取り組めば、テストの対策になります。
読解に関しては、全く同じ問題が出るわけではありません。
「自分なりの取り組み方」を見つけて、問題演習をして精度を上げていくことが大切です。
漢字・知識に関しては、選択肢で問われていたものが、書き取りで問われるなど、少々出題にアレンジが加えられていることもあります。
とはいえ、「出題されている内容」はテストも問題集と同じなので、取り組んでおくべきでしょう。
【文章のジャンル・読解テーマ】
11回 随筆文(1) 経験と感想①
随筆文とは、筆者が経験したことを「自由に」書き表した文章のことです。
「自由に」とありますが、中学入試で出題されるのは大きく3パターン。
①論説文に似たタイプ
②小説文に似たタイプ
③紀行文 です。
11・12回では、②小説文に似たタイプを学習します。
13・14回で説明文・論説文を学ぶので、テストの際に論説文のみにならないように「調整」されているのでしょう。
今回は「小説文に似たタイプ」の随筆文の出題とわかっているので良いのですが、
入試本番ではどのタイプが出るのかわかりません。
やたらと「私は」などの表現が使用され、随筆文と判定できたときには、どの文種に近いのかを正しく判断できるようにしましょう。
12回 随筆文(2) 経験と感想②
随筆文は、「筆者の経験」を元にして書かれています。
文の内容が「経験」か「感想」のどちらなのかを意識しながら読むのが大切です。
特に大事なのは「感想」で、こちらに筆者の思ったこと・意見が書かれています。
小説文に似た随筆文で文章に線を引くなら、「感想」の部分のみに線を引くのがおすすめです。
そうすれば、小説文と同じように文章を読み進めることができるでしょう。
主題に関しては、小説文で主人公の気持ちの変化に注目するのと同様に、筆者の気持ちの変化に注目しましょう。
13回 説明文・論説文(5) 要旨①
「要点」「要旨」「要約」など……
論説文においては、「要」とつく用語が非常に多いです。
今回は「要旨」に注目した内容となっています。
要旨とは、「筆者のイイタイコトを、文字数30〜50字で、文章の最後や最初から拾ったもの」を表す、と増田は教えています。
文章のタイトル・話題などをヒントに、「筆者のイイタイコト」をどう見つけるかがカギです。
多くの場合、文章の最後の方にイイタイコトがあることが多いですが、最後の段落が具体例で終わる文章も時々あります。
最終的に具体と抽象をきちんと読み分けて内容を判断する必要があるので、その点は注意です。
14回 説明文・論説文(6) 要旨②
13回の「要旨」の練習回②です。
13回で扱った内容とほとんど変化はありません。
2度練習する必要があるくらい、「要旨を取る」ことは重要であると予習シリーズの執筆者は考えているようですね。
そこに関しては私も完全に同意見です。
【知識問題】
11回 文節と文節の関係① 主語・述語・修飾語
文章読解でも深く関わりがある、主語・述語・修飾語について学習します。
こちらは予習シリーズ小4上の11・12回で学んだ内容の総まとめとなっています。
・倒置がかかっている場合は元の語順に戻す
・述語→主語の順で探す
・修飾語は、指定された傍線部の文節より下の文節に一つずつ繋いで、自然に繋がるものを探す
の3つを基準に、解き進めてみましょう。
12回 文節と文節の関係② 分けて<関係>を考える
11回で扱った内容の応用です。
長い一文の文の要点をどのように読み取るかが鍵となっています。
①一文全体の述語→主語を読み取る
②それ以外の述語→主語を探す
③その他の修飾語がどの文節につながっているか確かめる
④①〜③を行った上で、<大きな意味のかたまり>を見極める
⑤<大きな意味のかたまり>の間の関係を考える
という手順は長文読解の前の段階である、一文を正確に読み取る上で非常に重要な動きとなっています。
長文読解で苦労がある生徒さんは、この回の内容で不安があるケースが多いと感じます。
13回 文と文の関係① 接続関係①
接続語の復習回です。
順接・逆接・添加・並立…などの意味を言える必要は中学入試においては正直ありません。
ただ、「接続語の前と後でどんな内容の文が来る」ときに、どの「接続語を選ぶ」のかについてはできる必要があります。
「ところで」と「ところが」、「また」と「あるいは」を使って例文を作る、などの対策も有効だと思います。
14回 文と文との関係② 接続関係②
接続語の応用回です。
前回と同じような問題の他、代名詞(指示語)と絡めたちょっとした長文問題などの出題があります。
この回も要旨と同様、2度練習する必要があると考えられているようです。
私も完全に同意見です。
13・14回は長文読解において「雑に扱いたくない」回であると感じます。
四谷大塚・早稲アカ5年生 6月度組み分けテストについては以下もご覧ください。
四谷大塚・早稲アカ5年生 6月度組み分けテストはどう対策する?算数編
四谷大塚・早稲アカ5年生 6月度組み分けテストはどう対策する?国語編
四谷大塚・早稲アカ5年生 6月度組み分けテストはどう対策する?理科編
四谷大塚・早稲アカ5年生 6月度組み分けテストはどう対策する?社会編
にほんブログ村にも参加しています。ぜひ下のバナーをワンクリックで応援もお願いします!

-1.jpg)

.jpg)

.jpg)