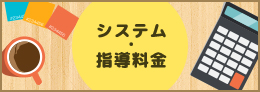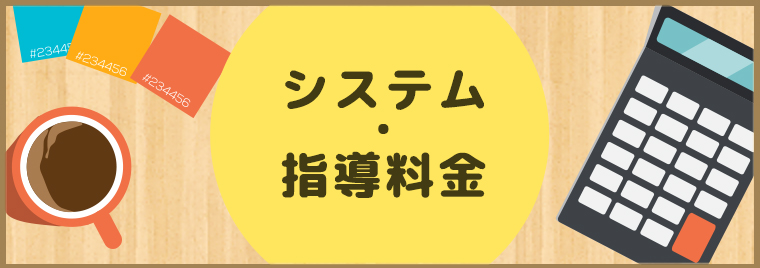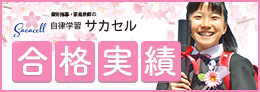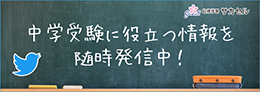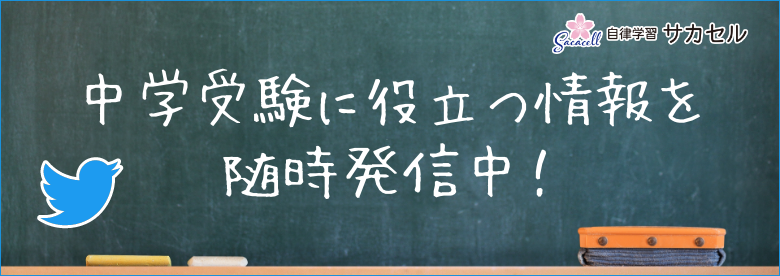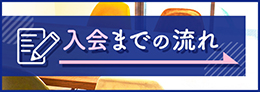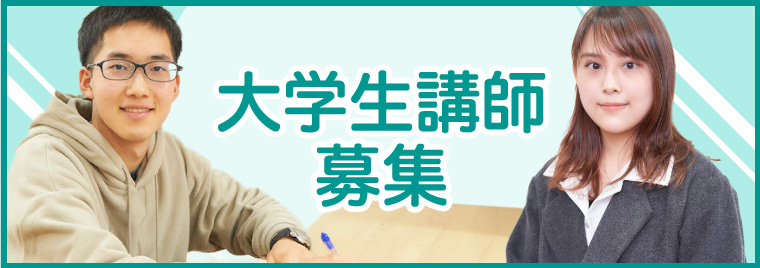2022年6月24日 投稿
2024年7月10日 更新
「夏休みのコースが決まる超重要な試験だ!」と多くのSAPIX5年生が気合を入れて臨んだ組分けテストから約3週間。
2024年は7月19日(金)に7月度復習テストが実施されます。
復習テストはコースの昇降がなく、またイベント目白押しの夏休みも目前と言うこともあり、今一つ気分の乗っていない生徒も少なくはありません。
ただ算数に関しては中学受験最重要単元の割合の学習が始まって初めての試験です。
絶対に軽視してはいけません。
ここからは7月度復習テストの算数の位置づけや出題傾向、対策などを整理してみましょう。
【7月度復習テストの概要】
実施日程:2024年7月19日(金)
制限時間:50分
配点:150点満点
試験範囲:平常14から平常18の全5冊と算数基礎力トレーニング6月号
平常14 割合(1)
平常15 総合(11~14)
平常16 割合(2)
平常17 割合(3)
平常18 割合(4)
直近3年の平均点は
2023年 80.7点
2022年 78.6点
2021年 90.3点
となっています。
範囲のあるテストらしく、やや高めの点数で推移しています。
【7月度復習テストにおける算数の重要度】
7月度復習テストから、いよいよ中学受験の算数の鍵になる「割合」が試験範囲として課されます。
抽象概念の理解を問う割合は「ただ答えが出せたら良い」という単元ではありません。
問題文を正しく理解し、□を用いて適切に整理することや、「全体の」「残りの」「●割増し」「●割引き」といった細かな条件に気を付けることなど、算数的な読解力や丁寧な作業力が必須です。
算数的な読解力や式での条件整理は今後の学習の全てに関わってくるので、今回の7月度復習テストの学習内容の重要度は非常に高いです。
【7月度復習テストの算数の各テキストのポイント】
平常14 割合(1)
割合の導入テキストです。
「割合はかけ算」「問題文の順番通りに□を用いて立式」という基本を身につけましょう。
成績にかかわらずC1を「常識」として吸収して解きこなせるようにする必要があります。
偏差値55くらいを目指すならば、D2まで必要でしょう。
D3およびD4は「倍数」や「条件整理」など他分野との複合分野になりますが、決して難度は高くはありません。
C1レベルが身についているならば、現在の偏差値にとらわれずに積極的にチャレンジしましょう。
BASIC1割合1章「割合の基本」を併用した学習も効果的です。
平常15 総合
平常11~平常14までの復習回です。
ただ内容は過去に扱った問題よりも難しくなっています。
偏差値60までの生徒の皆さんにとっては、確認編Cくらいまでのレベルを解きこなせるようになっておけば充分でしょう。
それ以上のレベルを目指す皆さんは確認編Dの内容も理解は必要です。
受験レベルで考えれば、このレベルの問題も典型題の範疇に収まります。
なお、このテキストでは「復習と演習編」②の大問3の「単位換算を含む割合の三用法」が最重要です。
面積や体積などの単位換算に不安がある生徒は今回を機に定着させておきましょう。
平常16 割合(2)
「相当算」の導入テキストです。
「何が何の何倍か?」を式や線分図で適切に整理しましょう。
B3、B4、C2などのクラスの人数の問題の導入時は線分図のほうが状況を整理しやすいでしょう。
ただ「多い/少ない」を生徒自身が上手く線分図に整理出来ないならば、早い段階から式での処理に慣れたほうが良いかもしれませんね。
「全体の」「残りの」などに気を付けて、問題文を丁寧に読み込む習慣も、このテキストを機に身につけておきましょう。
この掲載内容なら、まずはB3までとC1・C3をマスターすることが先決です。
次にB4・C2・D2までを適切な方法で解きこなせるようになれば偏差値60が見えておきます。
D1・D3・D4も決して難しくはありません。
D1やD3に関しては問題文の読み込み方と線分図での整理の仕方が鍵になります。
将来的には解きこなしたい問題なので、余裕があれば取り組んでおきましょう。
なおこちらはBASIC1割合の2章相当算を併用して学習できると、より理解を深めることが出来るでしょう。
平常17 割合(3)
「損益算」の導入テキストです。
「原価」「定価」「売り値」「利益」「1個あたり」「全体」などの用語にいち早く慣れ、適切に式で条件を整理することが必要です。
なお問題によっては線分図や面積図で整理することで状況を視覚化し、理解を深めることもできるでしょう。
まずは用語の理解を深めるために、AB全てとC1・C2・C4を正しく立式できるよう練習しましょう。
上記はどのコースの生徒にとっても必要です。
残りの問題もD4まで決して難しくはないので、先ほどの問題で損益の用語を正しくおさえられているならば、現在の学力状況にとらわれずにチャレンジしたいところです。
なおこのテキストはBASIC1割合3章損益算を併用して学習することで、理解を深めることが可能です。
平常18 割合(4)
「食塩水」の導入テキストです。
「食塩の量」÷「全体の量」=「濃さ」という基本を、まずは常識として身につけましょう。
C2・C3・D1のような食塩水のやり取りは、食塩/全体の分数の形で整理することで取り組みやすくなることでしょう。
面積図による整理に関しては、現時点では必須ではありません。
夏期講習で比を学んでから定着させることが出来れば充分です。
どのレベルの生徒も、まずはC3までを常識として身につけましょう。
C4やD1・D2は比を学んでから扱ったほうが、学習効果が高いでしょう。
このテキストに関してはBASIC1割合の4章食塩水その1を併用して学習できると、理解を深めることが可能です。
なおBASIC1割合5章の食塩水その2は比を学んでから扱わないと、意味がありません。
現時点では気にしなくて良いでしょう。
【7月度復習テストにおける算数の対策】
今回の試験範囲の該当テキストは、平常15の総合回のほかは全て「割合」を冠しています。
出題内容に偏りがあることは否めませんが、それだけ重要度が高く、また対策が点数に結びつきやすいので是非とも頑張りたいところです。
対策としては、まずはSAPIXの教材の総復習が最優先です。
各テキストで身につけるべき典型手法を正しく理解、吸収しましょう。
また割合はBASICも併用することで効率良く学習が可能です。
基本問題を数多く反復することで、いち早く「常識」として割合を身につけましょう。
そのほか割合に関しては塾による指導法の差や用語の差が少ないことを利用して、予習シリーズなど他塾の問題集を用いた類題演習も効果的でしょう。
もし手に入れることが出来れば7月度復習テストの過去問を併用した学習で仕上げられると完璧です。
「全体の」「残りの」「問われているのは何か」など、自身がミスをしやすいポイントを事前に確認することで、試験における注意の仕方が具体的になります。
復習テストが終わると、いよいよ夏期講習ですね。
算数のカリキュラムは復習内容を数回挟むと、いよいよ受験算数における最重要手法の比の学習が始まります。
秋以降は比の複合分野を毎週のように学習していくので、初期段階での正しい理解は必須です。
我流にならないようまずは集中してSAPIXの授業に参加し、BASICも併用して入念に復習を重ねましょう!
もし割合や比の学習においてお困りのことがあれば、重症化する前に是非ともご相談ください。
自律学習サカセルは皆さんを応援しています。
SAPIXに関して、より詳しく知りたい方はこちらをご覧ください!
塾選びから合格(または転塾)までSAPIX完全解説
SAPIX5年生7月復習テストについては以下もご覧ください。(順次追加されます。)
SAPIX5年生7月復習テストで押さえるべきポイント算数編
SAPIX5年生7月復習テストで押さえるべきポイント国語編
SAPIX5年生7月復習テストで押さえるべきポイント理科編
SAPIX5年生7月復習テストで押さえるべきポイント社会編
にほんブログ村にも参加しています。ぜひ下のバナーをワンクリックで応援もお願いします!



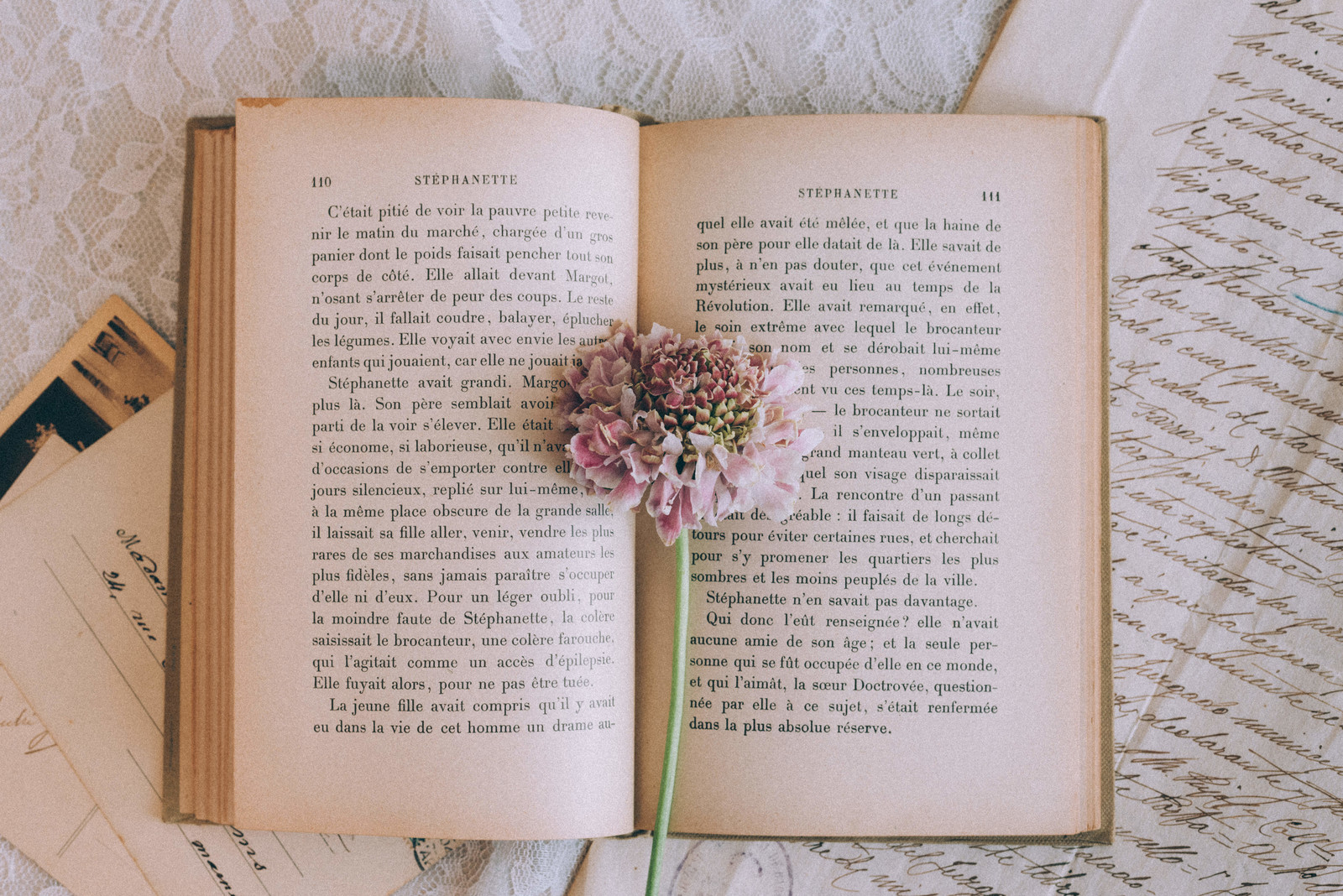

.jpg)

.jpg)