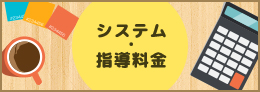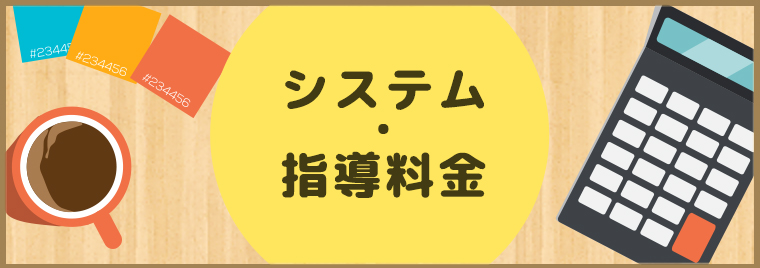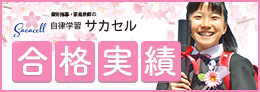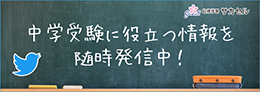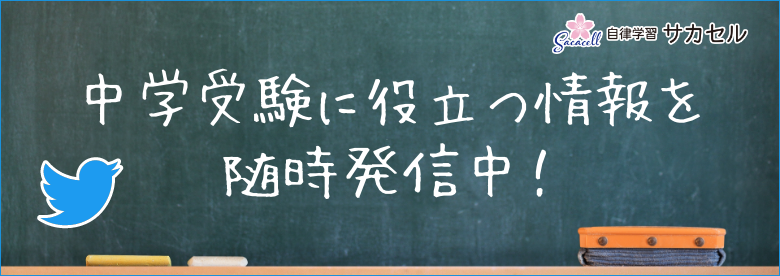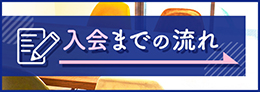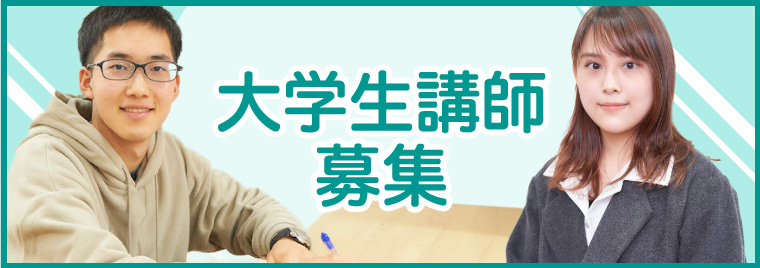2022年度に改訂があった、5年生の予習シリーズ。
私がこの仕事を始めてから3度、表紙が変わる大きな改訂がありました。
かつてあった「サブノート」が「演習問題集」の中に含まれ、「まとめてみよう!」というコーナーになる…などですね。
ただ、国語は大きく変わったところが多かったのですが、5年上の教材は前回の改訂と比較してそこまで大きな変化はありません。
●各回でおさえるべき内容のピックアップ
1回 魚はどこから?
・さけは生で食べなかった魚?
→チリ・ノルウェーで養殖されている
・水産業と人々のくらし
→おもな国の肉と魚の消費量の日本のデータ
・魚はどこでとれる?
→暖流・寒流の位置と名前、潮目・大陸棚が見られる場所と意味
おもな漁港の名前ととれる魚の種類
魚の取り方の図と名前を結びつけて覚える
・漁業の種類は?
→距離の近い順に養殖漁業<沿岸漁業<沖合漁業<遠洋漁業
漁獲量のグラフがどれを指すのかおさえておく、遠洋漁業は石油危機で1970年代に激減
・減っている漁獲量
→1970年代に石油危機で遠洋漁業が減少
1980年代に200カイリの漁業専管水域(排他的経済水域)の設定で沖合漁業が減少
1カイリが1852m、200カイリが約370km
・つくり育てる漁業
→養殖漁業は卵から成魚まで育てる
栽培漁業は卵から稚魚まで育てて放流
養殖される水産物の収穫量はできればベスト3まで言えるようにして、どこでどの水産物の養殖をしているか結びつけておく
・水産物が届くまで
→保冷トラックで魚市場に運ぶ、せりで値段が決まって買い取られる
・水産業の今
→高齢化と後継ぎ不足が問題
漁獲量ベスト2の中国・インドネシアはおさえておく
現在の水産物輸入額ベスト3はさけ・ます、えび、まぐろの順
海の資源を守るために魚付林を守っている
・持続可能な漁業とは
→持続可能な開発目標(SDGs)
マイクロプラスチック、エコラベルの名前と意味
2回 くらしに役立つ資源
・日本の都市に資源が眠る?
→レアメタル、都市鉱山の名前と意味
・日本の地下資源
→石炭、原油、液化天然ガス、鉄鉱石の輸入国ベスト3は必ずおさえる
日本のエネルギー供給の割合は頻出なので、石炭、石油、天然ガス、原子力、水力がそれぞれどれか見分けられるように
エネルギー革命の名前と内容(1960年代に起こったことも余裕があれば知っておく)
タンカーで原油のほとんど中東からを輸入すること、ナフサという名前と意味
液化天然ガスをアルファベットで答えるとLNG
・日本の電力(1)……地下資源を用いた発電
→火力発電の燃料割合、現在のベスト3は天然ガス>石炭>石油など
<2011>東日本大震災 の後から原子力発電はほとんど行われていない
日本初の原子力発電が行われたのは茨城県東海村、燃料はウラン
・日本の電力(2)……自然エネルギーを用いた発電
→再生可能エネルギー、化石燃料、メガソーラー、バイオマス発電という名称と内容
・おもな発電所とエネルギー源
→各発電所が主にどんな場所にあるのか、特徴と場所
発電のエネルギー源変化は水力、火力、原子力、自然エネルギーがどれがどれかをおさえる
フランスは石油危機の時に苦労したことが原因で原子力発電が中心、ドイツは東日本大震災の原発事故が原因で原子力発電を全て廃止
・これからのエネルギー
→頁岩から取り出され、天然ガスの代わりとなるシェールガス、石油の代わりとなるシェールオイル
二酸化炭素を排出しない水素エネルギー
3回 いろいろな工場 〜日本の工業(1)〜
・鉄鋼をつくる工場、なぜ広い?
→石油化学工業が有名な千葉県市原市(京葉工業地帯で化学工業の割合が高い理由)
鉄鋼=鉄鉱石+蒸した石炭(コークス)+石灰石
鉄鉱石と石炭はほぼ全て輸入、石灰石は自国でまかなえる
・工業とは?
→重化学工業と軽工業の中身、現在は重化学工業が中心
・金属工業……重化学工業(1)
→日本の工業生産額の割合は機械とせんい工業に注目
鉄鋼業は原料を輸入するので臨海部に作る
アルミニウムは大量の電力を必要とするので輸入と国内リサイクルが中心
・機械工業……重化学工業(2)
→おもな国の自動車生産台数は<2020>のデータで判断、多い順に中国>アメリカ>日本>ドイツ
関連工場、ジャストインタイム方式、流れ作業の名称と内容
日本の自動車の国内生産・海外生産と輸出台数は<2020>のデータで判断、多い順に海外生産>国内生産>輸出 で現在は現地生産が中心
おもな国の造船量は<2020>のデータで判断、多い順に中国>韓国>日本
集積回路(IC)は半導体を用いて作られる、人工知能の別名(AI)と区別する
・化学工業……重化学工業(3)
→原料を輸入するため臨海部にある石油化学コンビナート、ナフサの名称と内容
製鉄所と石油化学コンビナートがどちらもあるのは神奈川県川崎市、岡山県倉敷市、大分県大分市
・軽工業
→あたためるだけで食べられる調理済食品はレトルト食品
酒・しょうゆ・みそをつくるのは醸造業
石灰石が取れるところで発達するセメント工業(埼玉県秩父市が有名)
チップ・パルプの名称と内容
絹の原料である生糸は「まゆ」から作られる
・伝統をいかした工業
→伝統証紙、伝統的工業品を認定するのは経済産業省
伝統的工芸品は手作り・100年以上受け継いでいることが条件だが、輸入した原料で作成しても良い(漆はほとんどが輸入)
4回 うつりゆく工業のすがた 〜日本の工業(2)〜
・地場産業(じばさんぎょう)って何?
→地場産業で有名な福井県鯖江市(めがねのフレーム)、愛媛県今治市(タオル)、富山県富山市(製薬)
・工業のさかんなところ
→工業地帯・工業地域の生産額の割合は現在のデータでベスト3をおさえる、多い順に中京>阪神>関東内陸
太平洋ベルトの名称と場所
・工業地帯
→中京工業地帯
機械工業が65%超え(愛知県豊田市の自動車工業【TOYOTA】)
阪神工業地帯
せんい工業が1%超え(大阪府泉佐野市のカッターシャツ)
京浜工業地帯
機械工業が50%弱(神奈川県横浜市・横須賀市の自動車工業)
金属工業が10%弱、化学工業が20%弱(神奈川県川崎市)
※東京は印刷業がさかん
・工業地域
→関東内陸工業地域
機械工業が50%弱(群馬県太田市の自動車【SUBARU】)
化学工業が10%弱(海に面していないので原油の輸入がしにくく、京浜よりも割合が少ない)
瀬戸内工業地域
せんい工業が2%超え(愛媛県今治市のタオル)
東海工業地域
機械工業が50%超え(静岡県浜松市の楽器・オートバイ【YAMAHA】)
北陸工業地域
金属工業が15%超え(福井県鯖江市のメガネフレーム)
化学工業が10%超え(富山県富山市の製薬)
京葉工業地域
化学工業が40%超え(千葉県市原市の石油化学コンビナート)
北九州工業地帯(太平洋戦争よりも前にできたのが工業地帯なので、これを工業地域に当てはめるのは正しくないと感じます)
食料品工業の割合が全工業地帯・地域でトップ(福岡県福岡市の明太子)
機械工業が45%超え(福岡県苅田町【日産自動車】)
・日本の工業の今
→<1955>〜<1973>の高度経済成長により、工業の中心がせんい工業から重化学工業に
現在最も多いのは機械工業(自動車工業が中心)
電子部品は軽い・小さい・高額なのでトラックや航空機で運ぶため、空港・高速道路などの近くに作る
九州「シリコンアイランド」 東北自動車道「シリコンロード」
貿易摩擦・企業の利益の拡大のため1980年代から海外へ工場を移転し、現地生産が中心に
大工場と中小工場の工場の数1:99、働く人の割合3:7、生産額1:1は必ずおさえる
・工場と都市の関係は?
→企業城下町である愛知県豊田市トヨタ町、群馬県太田市スバル町、山口県山陽小野田市セメント町
★テストの構成・テキストの構成・対策と優先順位(毎度大きな変化はないため再掲となります)
【テストの構成】
35分 100点満点 配点・出題形式は一例です。
大問126点 書き取り10問 選択肢2問
大問246点 書き取り14問 選択肢9問
大問328点 書き取り4問 選択肢8問
35分で約50問。
傾向に変化がなければ、記述はなく、書き取りが中心の形式です。
一問一答の「名称」を問う形式がほとんどであるため、きちんと努力を重ねていれば報われやすい形式となっています。
これは昔から変わらずですが、「処理力」を重視した設問の構成となっています。
以前と変化があったのが書き取り問題で、一部のみ漢字指定だったのが、ほとんどの問題で漢字指定となっています。
自信のない内容は「ひらがな」で書けば◯がもらえる…という「安全策」が以前は取れましたが、難関校に向けた対応が必要になったと言えます。
【テキストの構成】
総合回以外の通常回 予習シリーズ
・テキスト解説ページ(ちょっとくわしく、今回のポイントも含む)
→基本的に太字を中心にチェックします。
太字の多くは「名称」です。
「名称」を中心に押さえるのが大切ですが、「名称を聞いた時に内容がきちんと言える状態」が望ましいです。
図・表・グラフからの出題も多いので、「どれが何を指しているのか」知っておくと良いでしょう。
【なぜそういった数値・グラフの動きになっているのか】までおさえておいた方が良いです。
塾の先生に質問する機会があるならば、【図・表・グラフを見分けるポイント】【目立つデータがあれば、なぜそういうデータになっているのか】を質問するのが良いでしょう。
・要点チェック
→比較的取り組みやすい一問一答です。
集団授業を受けているなら、授業後に一番に取り組んで欲しい内容となっています。
総合回 予習シリーズ
・学習のまとめ
→約4回分の内容を凝縮したテキスト解説コーナーです。
ここはそこまでチェックしなくて良いでしょう。
・要点チェック
→通常回とは違い、図・表・グラフからの出題が中心です。
比較的取り組みやすいので、なるべく早めに解くのが良いでしょう。
・練習問題
→組分けテストに近い形式の問題です。
配点はついていないですが、「組分けテストの過去問」と見て良い内容です。
予習シリーズの要点チェック、演習問題集のまとめてみよう!・グラフに書きこもう!・白地図に書きこもう!に一通り取り組んだ後にチャレンジしたい問題です。
総合回以外の通常回 演習問題集
・まとめてみよう!
→予習シリーズのテキスト解説ページを「穴埋め形式」にしています。
「名称」を中心に問う形式となっているため、早いタイミングで取り組みたい内容となっています。
・グラフに書きこもう!
・白地図に書きこもう!
→予習シリーズのテキスト解説ページに載っている内容のうち、「問われやすい問題」を中心にピックアップしています。
これも早いタイミングで取り組みたい内容となっています。
・練習問題
→予習シリーズに載っているものと同様、組分けテストに近い形式の内容です。
予習シリーズの要点チェック、演習問題集のまとめてみよう!・グラフに書きこもう!・白地図に書きこもう!に一通り取り組んだ後にチャレンジしたい問題です。
・発展問題
→入試問題をもとに、予習シリーズの該当回に合わせてアレンジを加えた問題となっています。
練習問題よりも難易度は難しめで、ここで初めて見る内容の問題も存在します。
余裕があるなら毎週のルーティンに組み込みたい問題です。
・記述問題にチャレンジ!
→入試問題をもとに出題される記述問題です。
難しい問題も含まれています。
この問題に取り組むなら、担当の先生などに採点をお願いしたいところです。
優先順位は少々下がります。
総合回 演習問題集
・練習問題
→組分けテストに近い形式の問題です。
配点はついていないですが、「組分けテストの過去問」と見て良い内容です。
予習シリーズの要点チェック、演習問題集のまとめてみよう!・グラフに書きこもう!・白地図に書きこもう!に一通り取り組んだ後にチャレンジしたい問題です。
4週間前に扱い、忘れてしまっている内容を思い出すきっかけにもなりますし、是非取り組みたい内容です。
・応用問題
→こちらも、組分けテストに近い形式の問題です。
配点はついていないですが、「組分けテストの過去問」と見て良い内容です。
予習シリーズの要点チェック、演習問題集のまとめてみよう!・グラフに書きこもう!・白地図に書きこもう!に一通り取り組んだ後にチャレンジしたい問題です。
練習問題よりも少々難しめですが、ぐんとレベルが上がるわけではないので、「聞かれ方の引き出し」を作るためにも取り組むことをオススメします。
・チャレンジ問題
→入試問題をもとに、予習シリーズの該当回に合わせてアレンジを加えた問題となっています。
通常回の発展問題と同じ立ち位置の問題です。
こちらも余裕があれば取り組んでおきたい内容となっています。
【対策と優先順位】
□通常回の予習型の塾の進め方の一例(四谷大塚など)
①テキストを読む
②太字を中心に、表・グラフ・図の内容などもチェックして内容をおさえる
③予習シリーズ通常回の要点チェックで内容の確認
★通っている塾で授業を受ける
★授業後、授業内で取ったノートなどを見返して記憶を整理する
④演習問題集のまとめてみよう!・グラフに書きこもう!・白地図に書きこもう!を取り組む(できれば参考資料なしで取り組みます。もし定着内容に自信がなければ予習シリーズでわからない問題を調べて取り組みましょう。わからなかった問題・調べた問題は別途印などをつけておくと良いです)
⑤演習問題集の練習問題に取り組む
⑥予習シリーズの練習問題に取り組む
⑦演習問題集の発展問題に取り組む
⑧演習問題集の記述問題にチャレンジ!に取り組む
■通常回の復習型の塾の進め方の一例(早稲田アカデミーなど)
①通っている塾で授業を受ける
②授業後、授業内で取ったノート・テキストでマークした箇所などを見返して記憶を整理する
③予習シリーズ通常回の要点チェックで内容の確認
④演習問題集のまとめてみよう!・グラフに書きこもう!・白地図に書きこもう!を取り組む(できれば参考資料なしで取り組みます。もし定着内容に自信がなければ予習シリーズでわからない問題を調べて取り組みましょう。わからなかった問題・調べた問題は別途印などをつけておくと良いです)
⑤演習問題集の練習問題に取り組む
⑥予習シリーズの練習問題に取り組む
⑦演習問題集の発展問題に取り組む
⑧演習問題集の記述問題にチャレンジ!に取り組む
毎週の取り組みで⑧まで取り組むのがベストですが、目指す偏差値によって何番まで取り組むかが変わってきます。
偏差値50〜55を目指すなら⑤〜⑥まで
偏差値60以上を目指すなら⑦まで
入試問題を見据えて取り組むなら⑧まで実施し、担当の先生に添削してもらう
というところでしょうか。
④までで終わりにする子も一定数いますが、「入れ込んだインプットの内容をアウトプットして確認する」作業を行っていないため、組分けテストに対応するのは難しいと思います。
せっかく取り組むならば、最低でも⑤もしくは⑥までをワンセットにすることをオススメします。
□総合回の予習型の塾の進め方の一例(四谷大塚など)
①通常回のテキストをざっと読み直す
②演習問題集のまとめてみよう!・グラフに書きこもう!・白地図に書きこもう!で印をつけたところを再度見直す
③予習シリーズ総合回の要点チェックで内容の確認
★通っている塾で授業を受ける
★授業後、授業内で取ったノートなどを見返して記憶を整理する
④予習シリーズの練習問題に取り組む
⑤演習問題集の練習問題に取り組む
⑥演習問題集の応用問題に取り組む
⑦演習問題集のチャレンジ問題に取り組む
■総合回の復習型の塾の進め方の一例(早稲田アカデミーなど)
①通っている塾で授業を受ける
②授業後、授業内で取ったノートなどを見返して記憶を整理する通常回のテキストをざっと読み直す、演習問題集のまとめてみよう!・グラフに書きこもう!・白地図に書きこもう!で印をつけたところを再度見直す
③予習シリーズ総合回の要点チェックで内容の確認
④予習シリーズの練習問題に取り組む
⑤演習問題集の練習問題に取り組む
⑥演習問題集の応用問題に取り組む
⑦演習問題集のチャレンジ問題に取り組む
こちらも通常回と同様⑦まで取り組むのがベストですが、目指す偏差値によって何番まで取り組むかが変わってきます。
偏差値50〜55を目指すなら④〜⑤まで
偏差値60以上を目指すなら⑥〜⑦まで
というところでしょうか。
練習問題・応用問題・チャレンジ問題に取り組み、なぜその答えになるのかがわかる状態になっていれば、かなりの点数が見込めます。
四谷大塚の組分けテストの社会は努力が反映されやすいです。
4科目の勉強のバランス・目指す偏差値からどこまで取り組むかを決め、進めていくのが良いでしょう。
にほんブログ村にも参加しています。ぜひ下のバナーをワンクリックで応援もお願いします!

.jpg)

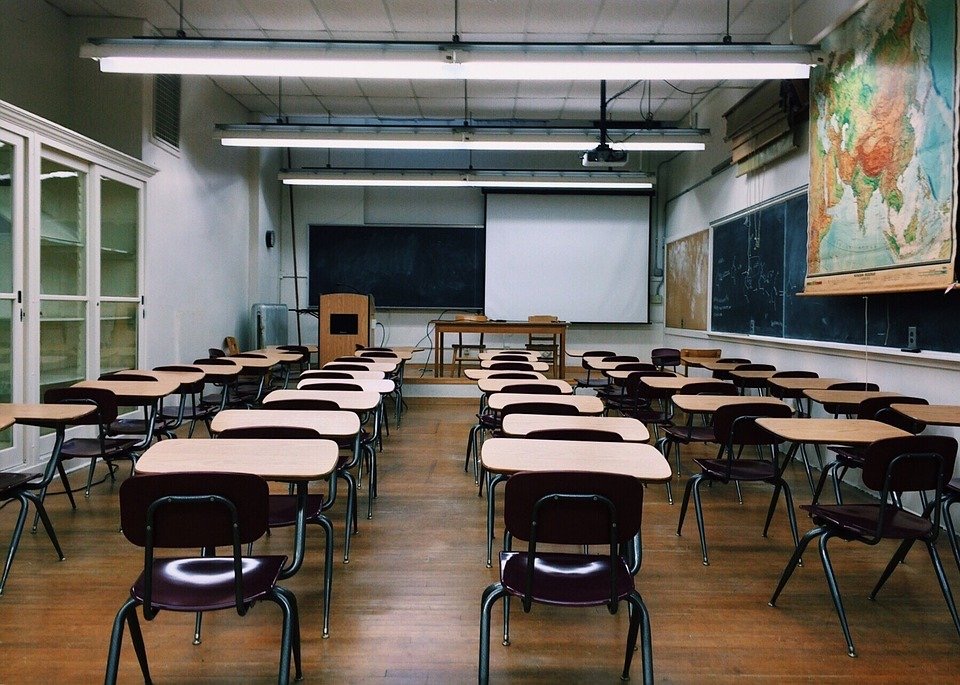

.jpg)