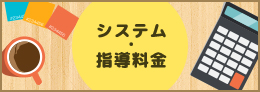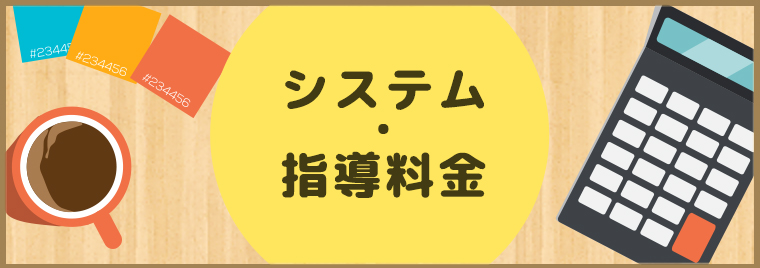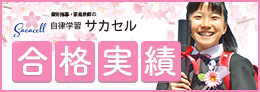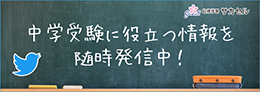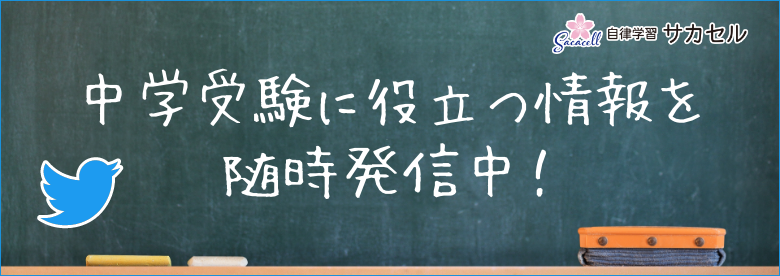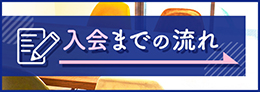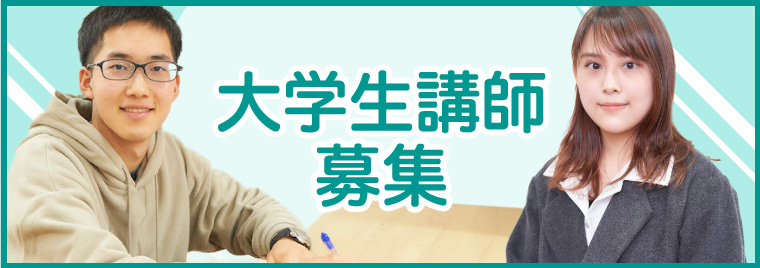増田の母「塾の宿題やったの?」
小5増田「いや、出てないよ」
増田の母「そんなわけないでしょ!」
小5増田(いや、本当に宿題なんか出てないんだけどなぁ…)
増田の母「いいからやりなさい」
小5増田「だから出てないって言ってるじゃん」
その後、親子で言い合いの喧嘩に…
新小5の2月から日能研に通っていた増田少年。
当時は「計算と漢字」「受験全解」「栄冠への道」などありましたね…(懐かしい)
「計算と漢字」の計算には●月●日と日付が割り振られていました。
1~2か月に一度「計算と漢字」を受付に提出する必要はありました(出しても「次回出してね」で終わりでした)。ただ、各科目の先生からの宿題は一切出ていませんでした。
これは「宿題」という指示がないだけで、
「授業内で導入」
→「栄冠への道で復習」
→「週末にカリキュラムテストで出来をチェック」
というのがシステム化されていたからなのでしょう。
だから明言する必要がない、と。
「授業内で宿題の指示がない」ということは、通っている生徒からすると「授業中に宿題は出ていない」という認識です。
生徒である小5増田少年からすると、「宿題がない」というのは真実です。
一方の増田の母。(ちなみに、中学受験の経験はありません)「塾の宿題やったの?」という言葉が「イイタイコト」ではありません。
【なぜ勉強もせずに遊んでいるのか】が「イイタイコト」なのです。
実質小4の増田少年に、そこまで理解するまでの能力も、相手の立場を考えることができる度量もありませんでした。
この喧嘩以降、専業主婦であった私の母は「勉強しなさい」と一切言わなくなりました。「勉強は自分でするもの」という考えに至り、私は放っておかれるようになりました。
また、私の父はその時何をしていたのかというと…
中学受験の経験者で、そもそも仕事が忙しい人でした。
基本的には母と同じで「勉強は自分でするもの」という考えでした。両親に勉強で「放っておいてもらえた」ことは自分にとって大きかったと感じています。
自分が生来「負けず嫌い」であること。
人に指図されるのが大嫌いであること。
塾の授業自体が新鮮で楽しかったこと。
勉強するタイミングをずらしたり、テストで理由の語尾を全部「ので」にしたりして、自分なりに試行錯誤できたこと。
10か月間、色々試して、一番下のクラスから一番上のクラスまで上がって成功体験を積めたこと。
何かを取り組む上で、「自分にとっての勝利の方程式を作れたこと」は大きかったと思います。
●喧嘩のデメリット
年を追うごとに問題の質が高まる中学入試。
「平成の初期の頃」と「令和の現在」を比べると、その問題の質の差に愕然とします。
「平成初期の灘中で出題された図形の問題」が、「近年だと偏差値55近辺の学校でも出題されている」というケースは珍しくありません。
年を追うごとに問題を解くための手法も洗練され、それに伴って問題も難化してきたというところでしょうか。
「質が高まった」ことで、「親が何も介入せずに受験を迎えられるケースは難しくなった」と言えると思います。
時代は常に変化しています。
ただ、喧嘩をするメリットがないのは、昔も今も変わっていません。
「怒りなどの感情を、当の本人に直接ぶつけることができる」ということくらいでしょうか。
デメリットとしては
-
エネルギーを必要以上に消費する
-
家族内の雰囲気が悪くなる
-
関係修復に時間がかかる
-
親も子どもも、「その後何かをする気力」が失われる
などが考えられます。
「集中した勉強時間」を「どれくらい積みあげられたか」が問われる中学入試の勉強。
ストレスを抜ける趣味の時間ならまだマシですが、ストレスを溜める喧嘩に貴重な時間を費やすのは、はっきり言って時間の無駄です。
その後の勉強時間の期待値まで含んで考えると、浪費と言わざるを得ません。
お金で買えない「時間」をドブに捨てています。
●喧嘩が発生する原因(親)
子どもは「他にやりたいことができない」ことが喧嘩の原因であることがほとんどですので割愛します。
①親のやる気>子どものやる気
一般的に「中学受験は親の受験」、また「中学受験は親子の受験」と言われます。
小学生の間までは、親の介入度が必然的に高くなります。
中学受験をさせようと考えるのは親がきっかけであることがほとんどです。
「子どもの可能性を広げてあげたい」という思いは、子を持つ親なら誰しもが考えることではないでしょうか。
中学生のうちから同じような価値観で話ができる友人がいるというのは、恵まれた環境であると言えるでしょう。
中学受験はそれを実現できる良い機会、と言えます。大人になるまでに様々な経験をしているからこそ、その機会が貴重で尊いものであるとわかります。
ただ、それを経験していない子どもにはその事実がわからないし、伝えてもなかなか伝わりません。
そのギャップが原因で喧嘩をしてしまうことは多いのではないでしょうか。
②他の家の子どもとの比較
「同じクラスの○○ちゃんは、朝5時に起きて勉強しているらしいよ」
「●●クラスの子は当然これくらいはやってるよ」
「○○くんは1週間分のテキストを3周もしているらしいよ」
「○○さんは◆◆(自分の本当にやりたかった習い事)をやめて勉強に集中しているらしいよ」
など、ついつい他人と比較してしまいがち。
自分の子どもだからこそ、出来る出来ないの2択であれば、「出来る」側でいて欲しい気持ちなどの裏返しだと思いますが…
子どもは「憧れの人」でもないなら、別にその他人になりたくて生きているわけではありません。
③親自身のストレス
自分の思い通りにならないことの多さ、しなければならないことに対しての負担、関わりたくない人たちとのやり取りなど…
様々なことでストレスを抱えています。
ストレスを溜めて何かをしているときに、目の前にいる我が子がやるべきことをやらずにグダグダしている…
そうなると、我が子が「ストレスの捌け口」になってしまいますね。
子どもも親も、同じ人間ですからね。
●結論
喧嘩は「しない」に尽きると思います。
時間を消費するなら、「建設的」に物事が進むように親の方からサポートする方が良いでしょう。
①怒りたくなったら、「怒る原因になった1点のみ」に言及する
家の中で「宿題」や「タブレット」などの使い方のルールを決めるなら、
「それが守れなかったこと」のみを注意する、などですね。
例えば、「勉強する」と言った子どもの過去の発言まで遡って叱責したり、怒る原因以外の「怒りたくなるような子どもの行動」にまで波及させて叱責しても、
子どもはただ塞ぎ込むだけです。
言い方が悪いですが、ただの「ガキ」なんですよね。
発言に対しての責任感も、自らの力だけでお金を生み出すことも、何なら自分の行動が周りにどう影響するのか考えるかもできない「ガキ」なんです。
どんなに賢く見えたって、精神的に未熟な子どもなんですよね。
未熟だからこそ、熟した立場の人間が「考える機会」を与える。子どもだって何も感じないわけではありません。
改善点を探るために、家族みんなで話し合いをするのも良いと思います。
物事は建設的に進められた方が良いですしね。
②「○○しなさい」という命令口調→「○○は終わった?」「〇〇はもう始めている?」という事実を確認する言い方に
「◯◯しなさい」という言い方は、いくら子どものための方策であったとしても、「他人からの命令」であることに変わりありません。
子どもは「自分が主体となる行動」でなく「親が主体となる行動」だと感じるんですよね。
特に、後でまとめてやろうと思っていたことが仮にあったとして、それを逐一「◯◯しなさい」と誰かに言われるのは、大人だってストレスを感じるはず。
「事実を確認する」聞き方であれば、基本的に返答はイエスとノーの二択です。
イエスなら「良く頑張ったね」ですし、ノーなら「いつやるの?」です。
ちなみに、増田の授業においては「本文への線引き」「設問への書き込み」を推奨しています。
「直し」を進めるときには基本的にその2つから取り組みます。
授業に慣れた生徒が、各種書き込みをしていないときは設問や本文を見て、「白いなー」と一言伝えています。
生徒はそれを聞いて、「するべき作業」をします。
習慣と化しているのもあるでしょうが、皆なんだかんだ「成長」するんですよね。
③比べる相手は、他人ではなく「過去の自分」
人間は、「比較」をしがちです。
ただ、何月何日何時に生まれたという話から親の仕事まで、何から何まで違う他人と比較しても、建設的な話にはなりません。
「●●ちゃんのパパは、週に3日朝食と夕食を作ってくれて、風呂掃除も洗濯もやってくれるの」などと言った話を、妻が夫にチクリと伝え、「妻側」の立場のコメンテーターが妻の立場からあれこれ言う話……ワイドショーなどで聞くことはありますね。
自分が実際にこれを言われたことは一度もありませんが、大人の自分でも「されたらひたすらに不愉快」です。
立場をひっくり返して「●●ちゃんのママは…」という話にした場合でも、その「不愉快さ」は変わらないでしょう。
比べるなら、「過去の自分」とが良いでしょう。
「何かが出来なかった」のが「何かが出来るようになった」のが精神的な「成長」です。
「昨日の自分」と比べて、これが出来るようになった。
「さっきの自分」と比べて、これが出来るようになった。
基本的に「出来るようになった」で会話を終われるため、前向きな話になりやすいでしょう。
●あとがき
私は、自分の生徒に伝えていることがあります。
それは「親子喧嘩の99%は子どもに原因がある」ということです。
「なぜ喧嘩したのか」を聞いて、「まともな言い分を伝える子」はほとんど存在しません。
「まともな言い分を伝える子」は、そもそも喧嘩しないことがほとんどです。
また、仮に身体が大きかったとしても精神的には「子ども」です。
目的のために何かを「我慢して耐え抜く」なんてこと、できないです。
「目標に向かって走り出す」きっかけは、「大人の側のひと工夫」にポイントがあると思います。自分の感情に流されず、「建設的」な声がけについては、私も心掛けなければならないですね。
にほんブログ村にも参加しています。ぜひ下のバナーをワンクリックで応援もお願いします!

-1.jpg)