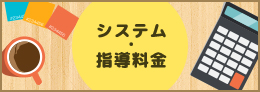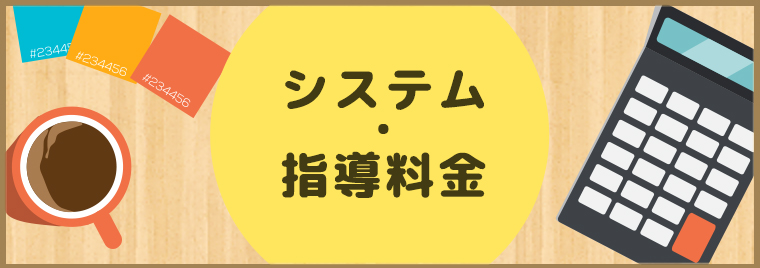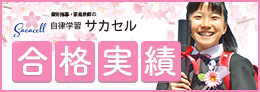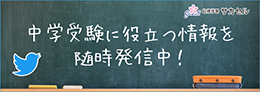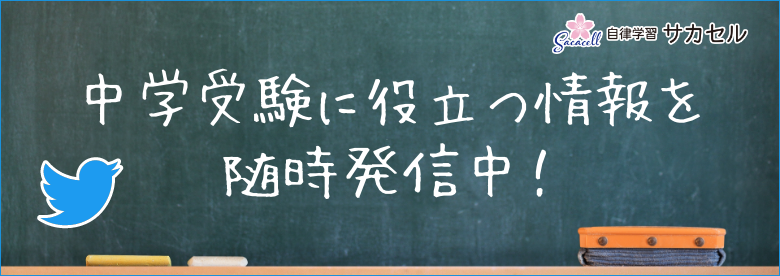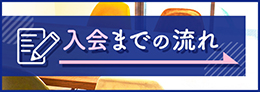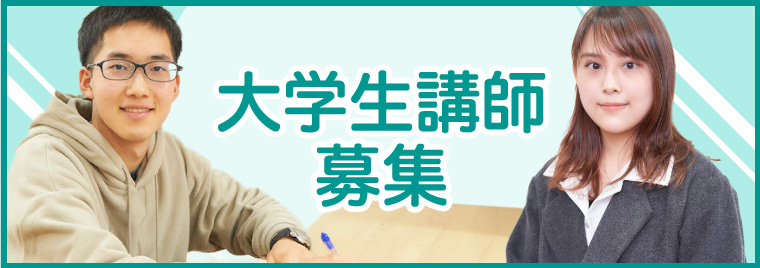小6の9月も終わり、もう10月…今からでも個別指導は受けるべきでしょうか?
実は毎年一定数聞かれるお話です。
志望校・成績状況・もろもろの事情はありますが、まともな指導を行っているのなら、受けないよりも、何かしらの効果があるのは間違いありません。
ここからは、「限られた期間でどういった指導を受けるのが効果的か」についてお話していこうと思います。
●効果的に働くケース
①「過去問の点数を上げたい!」
一番多いのがこのケースです。
私の担当している国語・社会で言うなら、「記述問題が多く出題される学校」を検討しているときに、この相談が多いです。
言うなれば、塾で定期的に受けるテストの形式と、志望校の出題形式に乖離があるときに、そこの差を埋めるイメージでしょうか。
最後の方の大問で、きちんと1問目は正解できるようになるようになど、「点数UP」が最終的な目標ですが、色々な形でのお願いをされます。
②「苦手科目を何とかしてほしい!」
次に多いのがこのケースです。
この科目だけがコンディションが上向かない。
転塾した時に、結局授業で導入される機会のなかった、特定の単元だけに苦手意識がある。
そもそもどこから手を付けてよいのかわからない。
これは、「単元ごとの得意不得意の見極め」「志望校の出題傾向」「現状の知識事項のある・なし」などを把握することが大切です。
③「志望校別コースの教材の消化を手伝ってほしい!」
次に多いのがこのケースです。いわゆる「四大塾」であれば、
-
SAPIX…SS特訓
-
早稲田アカデミー…NN志望校別コース
-
四谷大塚…学校別対策コース
-
日能研…志望校別日特クラス
が「志望校別コース」となります。
大手塾に通う小学6年生の、「テキストの消化スケジュール」に関しては恐ろしさすら覚えます。
例えばSAPIXの生徒さんなら
通常授業の宿題…①国語A・②国語B・③算数A・④算数B・③社会・④理科
土曜特訓の復習…⑤国語 ⑥算数 ⑦社会 ⑧理科
SS特訓の復習…⑨国語 ⑩算数 ⑪社会 ⑫理科
入試演習の実施と復習…⑬国語 ⑭算数 ⑮社会 ⑯理科
テキストを細分化せず、「科目名」だけで分けても16種類。
細分化して、テキスト名やテスト名に置き換えると、こなすべき課題は100をゆうに超えるでしょう。
志望校別コースに通っている他塾の方も、同じような数字になると思います。
志望校対策に直結する教材を、どう消化するか・授業で扱っていないが重要度の高い箇所はどこか・どこがカットできるところなのかなどを判断するのは難しいでしょう。
①~③に共通するのは、
生徒のコンディションや理解度を「判断」した上で、志望校に出題される問題や形式などの「傾向」を押さえ、必要な内容を「取捨選択」する力が、講師側に求められているということです。
10月以降で体験授業を検討する際は、これらの「判断」「傾向」「取捨選択」ができるかどうかを含めて見てみるのが良いと思います。
●効果的に働かないケース
①目標校と自分の実力が乖離しすぎている場合
目標としている開成中のSAPIX偏差値は4科67。
先日の9月サピックスオープンの偏差値は4科47。
いくら傾向が違うとは言っても、前提として求められる知識事項が少ない、などのケースだと、相当厳しいと言わざるを得ません。
目安は、現時点での偏差値の乖離が10で、「やり方次第でワンチャンス生まれる」かどうか。
1科目だけ数値が足りていない・この傾向の試験形式だけ点数が作れない、などとは種類が違う、と言わざるを得ないケースです。
②家庭でやってほしいことがはっきりしすぎているケース
これは一例を挙げてみます。
ご家庭「算数で開成に受からせてくれ」
担当「比の概念が怪しいからそこから導入し直したいんですが…」
ご家庭「そんなのはどうでも良いから、とにかく開成に受からせてくれ!」
などのケース。
入試問題で太刀打ちできるようにするためには、知っておくべき知識事項・考え方など段階を踏んで習得するべき内容があります。
それを全て飛ばして、結果だけ求める場合、担当とご家庭でコミュニケ―ションをきちんと取る、ということすらできず、結果もついてこないでしょう。
過程を飛ばして、結果だけ求めるというのは、仕事と同様、勉強でも難しいです。
③「6年の最後の最後」などの短期ではない時期の、単元にしぼった短期受講
例えば、「ニュートン算が出来ないので、ニュートン算だけ教えてほしい」というケース。
「ニュートン算の導入」から入るか、
「ニュートン算の演習」から入るか、
それ以前の「比の概念の導入」から入るかなど、
どこから導入すべきなのかは生徒さんの理解度・習熟度・基礎学力などによって変わります。
判を押したように「じゃあニュートン算の演習から…」としても、それが有効であるというケースは稀でしょう。
特に、「5年前期までの算数」で、単元に絞った受講は特に意味がありません。これは「比の導入」により、解くときのアプローチが大きく変わるからです。
また、4年の12月から5年の1月までの「2か月間だけ受講したいです」などのケース。
これも上手く行かないケースがほとんどです。
受講している間は上手く勉強のペースが作れても、いざ個別指導・家庭教師の手を離れると、せっかく上手くいっていた「流れ」が上手く継続できないまま1年が過ぎ、「積み重ねが上手くできていない」状態で時間を過ごしてしまった生徒さんが1年後に戻ってくる、というケースはよく耳にします。
●まとめ
短期の個別指導・家庭教師の利用について紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。
効果的に働くケース・働かないケースの2つをご紹介しました。
受験まで残り少ない期間だからこそ、後悔のない選択をしたいところ。
ちなみに、サカセルの講師陣は「取捨選択ができる」ことが強みなので、「限られた時間で効果的な指導」を行うのは得意であると言えます。
ご相談などある場合は、お気軽にサカセルまで。
サカセルでは、中学受験に関する皆様のご質問やご相談に中学受験のプロが回答いたします。お困りの際にはお気軽に下のお問合せフォームよりご連絡ください。
にほんブログ村にも参加しています。ぜひ下のバナーをワンクリックで応援もお願いします!

.jpg)

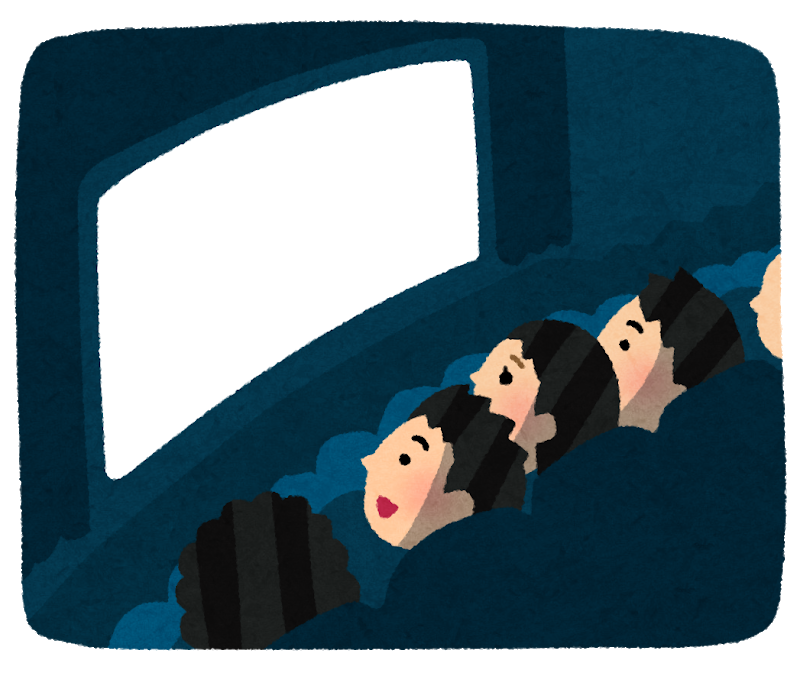



-1.jpg)